小学校と同じく、公立中学校の転校も大きく4パターンに整理できます。
結論から言えば、最も一般的なのはパターン1(住所変更あり)。一方で、中学校は教科担任制・定期テスト・評定(いわゆる内申)・部活動・高校進学という固有の事情が絡むため、同じパターンでも“押さえどころ”が少し変わります。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、公立中学校の転校を4パターンで整理。住所変更/指定校変更・区域外就学/公私間の行き来/特例の違いと、内申・定期テスト・部活への影響、必要書類など手続きについて、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
目次[非表示]
パターン1. 住所変更あり(住民票を動かす最も一般的な転校)
住所を変更するパターン1は、小学校と同じく中学校においても、最も一般的な転校のパターンです。
住民票を新住所に異動し、教育委員会が指定する通学区域の公立中へ転入します。基本の流れ(旧校で書類受領→役所で住民異動と就学先通知→新校へ提出)は全国ほぼ共通です。
- 旧校でもらう主な書類:在学証明書、教科書(教科用図書)給与証明書(*1)
- 役所・教育委員会でもらう主な書類:転入学(就学)通知書 等(*2)
注意点
パターン1に限ったことではないですが、中学校の転校に関しては主に次の3点を注意しましょう。
- 定期テストの切れ目:可能なら定期テストの前後で動くとスムーズ。やむを得ず途中でも、テスト範囲・追試・提出物の扱いを早期に確認しましょう。
- 評定(いわゆる内申)の継続性:通知表の写し・提出物・ノートがあると、転入先の評価がつけやすくなります。最終的な評定は転入先校の基準・在籍期間の記録で総合判断されます。
- 教科ごとのギャップ:教材・単元配列・評価観点が学校で微妙に違うことは普通。最初の2〜3週間を“追いつく期間”と割り切り、必要単元だけ重点補習が必要です。
パターン2. 住所変更なし(通学先だけ変えたい)――指定校変更/区域外就学
パターン2は、今の住所のまま別の公立中学校へ通うパターンです。住民票は動かさないので、同一自治体内で学校を変える「指定校変更」、または自治体をまたいで通う「区域外就学」を申請します。
いずれも審査・承認制のことがほとんどで、受入校の余力(教室・教員・学級規模)が前提。“申請=必ず許可”ではない点が最大の特徴です。
✔パターン2が当てはまる人の例
- 兄弟姉妹が同校に在籍しており生活動線を揃えたい
- 通学の安全(長距離・経路の危険・保護者の送迎事情)
- 健康上の配慮/医療的ケア(通院先との動線・学校側の体制)
- 教育的配慮:通級・特別支援学級の設置状況/校内教育支援センター(別室登校)運用/教育支援センターや学びの多様化学校との連携
- いじめや深刻な対人不安など、環境変更に合理性がある場合
注意点
パターン2の場合、特有の注意点がいくつかあります。
- “承認制”が大前提:各自治体は基準に照らして個別審査し、学校運営上の支障があれば不承認。そもそも在校中の学区外転校は原則認めないという運用もあります。
- 通学の安全確保は“保護者の責任”の明記例もあり:越境通学を許可しても安全確保は保護者責任とする自治体の案内があります。長距離・危険経路は不許可の判断要因にも。(*3)
- 通学費の扱い:多くの自治体の遠距離通学費補助は指定校への通学が条件で、区域外就学(越境)や指定校変更の児童生徒は対象外としている例あり。(*4)
パターン3. 公私間・国私立との行き来(公立↔私立・国立)
パターン3は、公立から私立、または国立へ、あるいは私立・国立から公立へ中学校を切り替えるパターンです。私立・国立中学校は、募集学年・実施時期・定員・選抜(学力試験/面接/書類)を学校ごとに定めます。
欠員時のみ募集の学校も多く、希望時期に“枠がない”ことは珍しくありません。出願要項に成績資料(通知表)や在学証明、健康情報の提出が明記されているのが一般的(*5)です。
注意点
特に私立・国立中学校へ転校する際には下記の注意点があります。
- 学力到達のギャップ:進度の早い私学・附属では学力の差が大きくなりがち。補習用の教材を学校に相談(朝学/放課後補習)。
- 学校文化の違い:校則・所持品・ICT運用・保護者会の関与度は幅広い。見学会や転入希望者向けの相談会などに積極的に参加を。
- 費用と戻り方:学費・諸会費・模試費・行事費に加え、公立へ戻る場合の手続きも確認。就学援助の適用可否は自治体で異なるため要照会。
パターン4. その他(海外・帰国・長期滞在/安全・福祉・医療・支援/学校・地域事情)
パターン4は、ここまで紹介した1~3には当てはまらない事情に基づいて在籍先を調整するパターンです。
ここでは「海外・帰国・長期滞在」「安全・福祉・医療・支援」「学校・地域事情」の3つのケースに分けて説明します。
ケース1.海外・帰国・長期滞在
帰国時は、日本語指導の受け方が自治体で異なります。教師が在籍校へ出向く派遣型もあれば、国際教室などの拠点校に通う方式もあり、後者では拠点校に通えるよう指定校変更や区域外就学の調整が行われることがあります。
学習面では英語・数学を中心に単元のズレが生じやすいため、転入時点で簡単な診断テストを行い、8〜12週間程度の補習計画(どの単元を、どの教材で、いつまでに)を先に設計しておくと、その後の授業にスムーズに合流できます。
ケース2.安全・福祉・医療・支援
在籍校を替えずに環境を調整する手段が増えています。
具体的には、通常学級に在籍しつつ必要時間だけ支援を受ける通級、少人数で学ぶ特別支援学級、教室以外で落ち着いて過ごせる校内教育支援センター(別室)、学校外の教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールとの併用、そしてオンラインを取り入れた在宅学習といった選択肢です。
入院や長期療養の際には、病院内学級(分教室)や訪問教育を使って学習を継続し、退院後は短時間・別室から始める段階的な復帰計画を組むと負担が少なくなります。
ケース3.学校・地域事情
学校統廃合や耐震工事、災害発生時などには、一時的に学区を変更したり、近隣校が弾力的に受け入れたりする運用が取られることがあります。
こうしたケースでは、在籍の扱い(どこに学籍を置くか)、通学手段や期間、必要書類といった実務の細部が自治体で異なるため、教育委員会に早めに相談し、手続きとスケジュールを確定しておくことが大切です。
*1 「市立小中学校転学の手続き」さいたま市/「区外からの転入」大田区/「市内転居する場合」大阪市
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
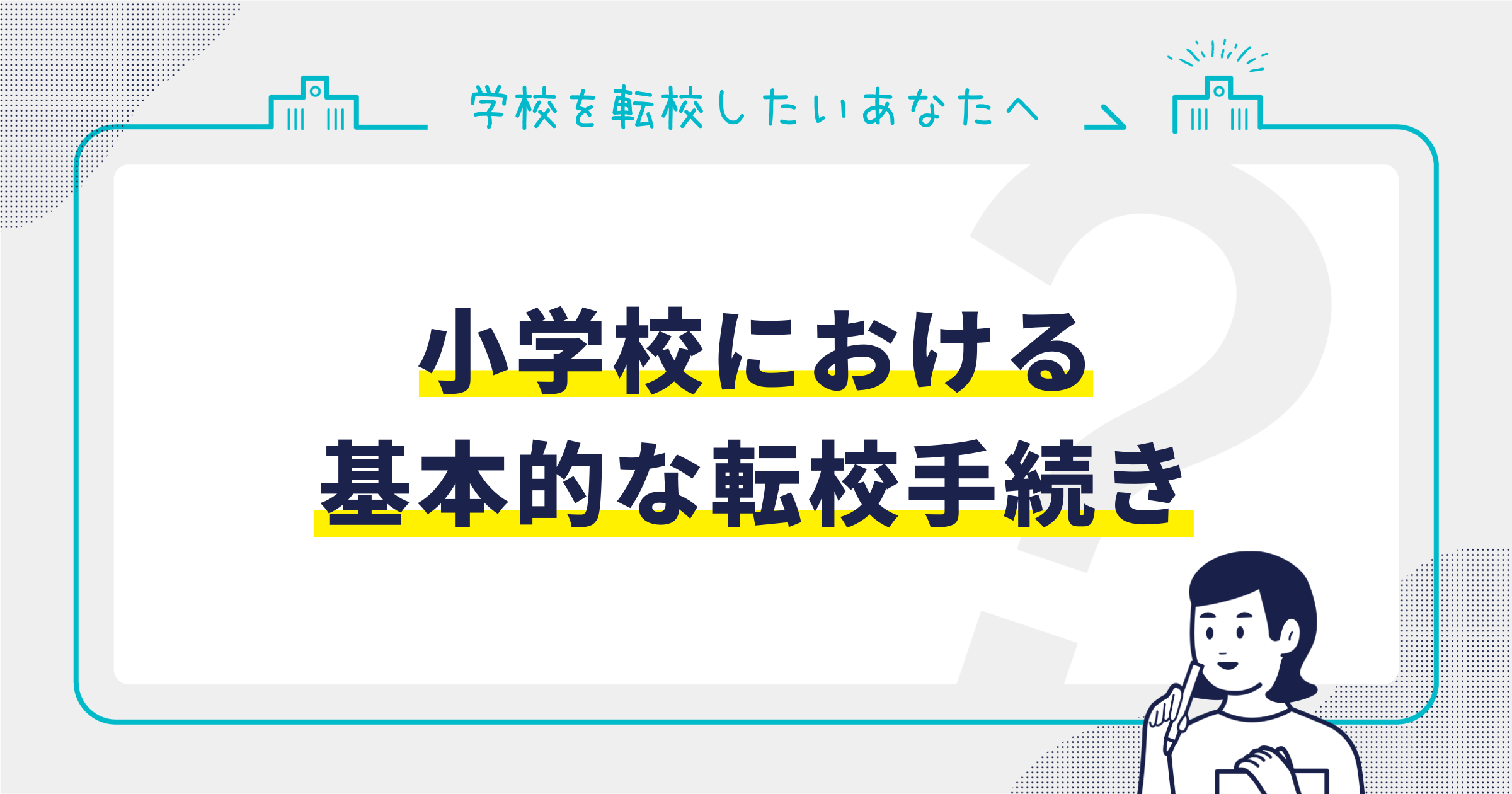
小学校における基本的な転校手続き

