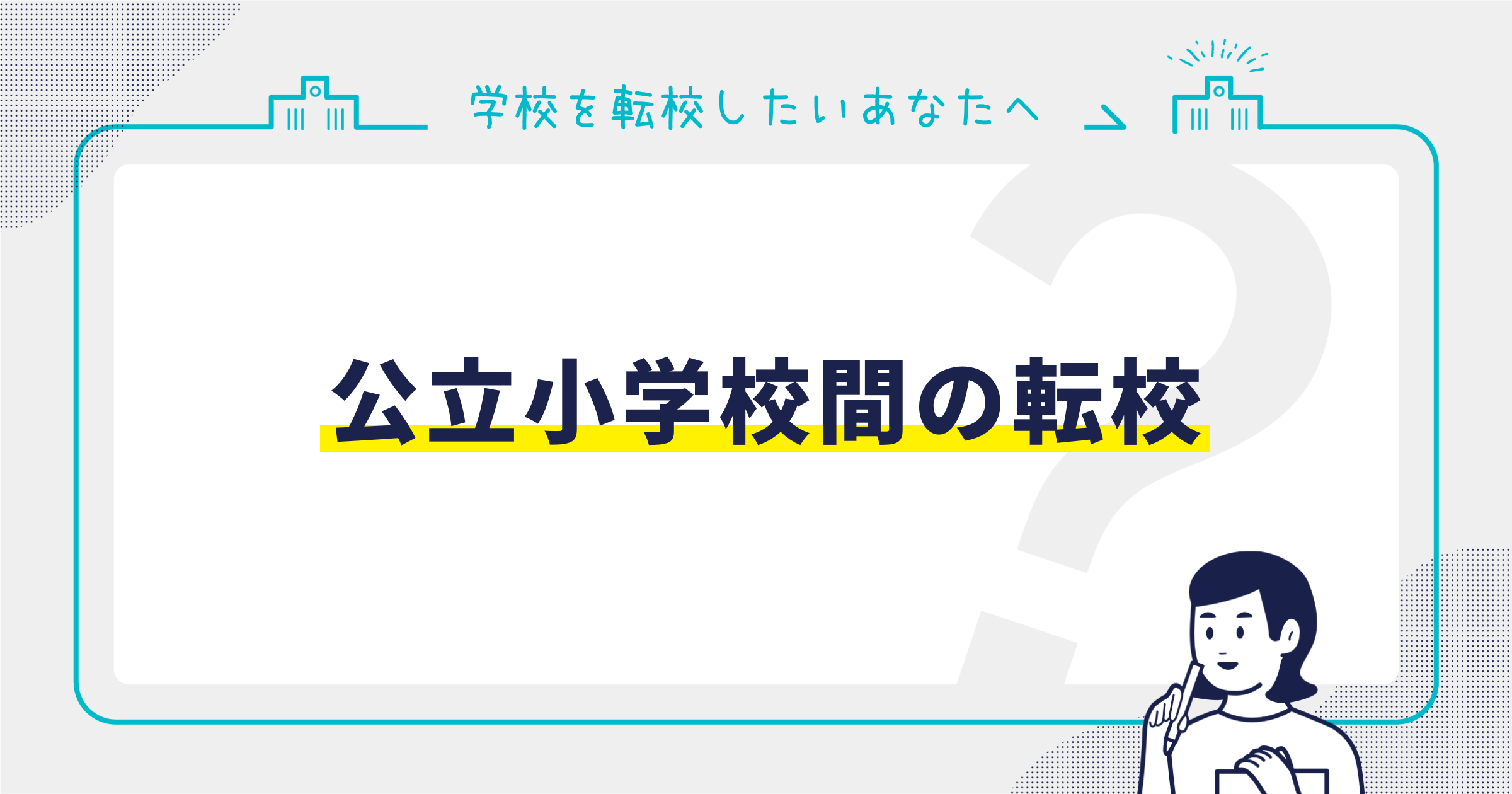小学校の転校は、大きく4パターンに整理できます。
小学校の転校を考える方にとって大切なのは「自分はどのパターンに入るのか」をまず知ることです。なので、ここでは各パターンの概要、注意点、当てはまる人を解説します。
ちなみに、公立小学校は自治体(教育委員会)が住所にもとづき指定校を決める仕組みが土台です。この「住所=基本」の考え方が、これから解説する4パターンの前提にあります。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、公立小学校間の代表的な転校のパターン4つを、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
パターン1. 住所変更あり(住民票を動かす)
パターン1は、もっとも一般的な転校のパターンです。小学校の就学は、住所にもとづいて教育委員会が就学校(指定校)を定める仕組みなので、家族が引っ越して住民票を変更すれば、新住所の通学区域にある学校へ在籍を切り替えるのが基本となります。
注意点
生活と学習の細部が学校ごとに異なる点は見落とされがちです。
校内ルール(持ち物・帽子・上履きの色や形)、連絡手段(連絡帳/アプリ)、放課後の過ごし方(学童の有無・定員・開始時期)などは学校や自治体によって差があります。
例えば、体育館シューズの記名ルール1つとっても学校ごとに異なります。
- 豊中私立刀根山小学校:体育館シューズには「体」と記入。ゴム部分に記名。(*1)
- 豊中私立箕輪小学校 :体育館シューズの甲に○体と名前、かかとにも記名。(*2)
さらに、自治体によっては新居の入居前から転居予定地の学校に通える「先行通学」や、学年末まで元の学校に「在籍継続」できる特例を設けている場合がありますが、可否や条件(入居時期の確定、契約書類の提示など)は地域差が大きい点に気をつけましょう。
✔「先行通学」の自治体
- 金沢市:「概ね6カ月以内」に転居が確定し、契約書類などで証明できれば、転居予定地の通学区域の学校へ今から通学可能。(*3)
- 世田谷区:「おおむね1年以内の引越しが確実で契約書等で確認できる場合、指定校変更の申請ができる」と明記=実質「先行通学」を許容。 (*4)
- 熊取町:「住宅の新築・購入等で転入・転居予定地校区の学校へ就学希望する場合、就学日から予定日が1年以内なら指定校変更を認める」と基準表に明記。 (*5)
- あきる野市:指定学校変更基準で「転居予定」を理由に、転居先の指定校へ就学を認め、承諾期間は“就学した日から転居する日までと明記。 (*6)
✔「在籍継続」の自治体
- 世田谷区:「学期末まで引き続き通学」や「最終学年は卒業まで通学」を区内転居時に認める旨を案内。さらに転居後の継続通学の電子申請ページも用意。 (*7)
- 新潟市:小4以下は最長で学年の終わりまで、小5以上は最長で卒業まで転居前の学校への就学を認める「学区外就学認可基準」があると案内。(*8)
- 渋川市:「学期途中で転居した場合、学期末まで/最終学年は卒業まで転居前の学校に通学可」と記載。(*9)
当てはまる人(例)
- 転勤・住み替え・住宅購入などで生活拠点が変わる
- 同一市内でも学区境界をまたぐ小さな引っ越しをする
- 新居完成に合わせて年度途中に通学先を変える可能性がある
パターン2. 住所変更なし(住民票はそのまま・通学先だけ変えたい)
パターン2は、住民票はそのままに、今の住所から別の公立小へ通うパターンです。
仕組みは2つで、同じ自治体の中で学校を変える「指定校変更」と、自治体をまたいで別の公立へ通う「区域外就学」。どちらも申請・審査・承認というハードルの伴う例外的な運用で、申請すれば必ず通れる制度ではありません。
✔ 同一自治体内で学校を変える「指定校変更」の具体例
- 世田谷区:「指定校変更は、基準に該当し、かつ学校運営や施設の受入状況から見て支障がないときに許可」といった旨の明記。審査では追加資料の提出や学校での面談を求める場合がある旨も記載。(*4)
- 台東区:「特別な理由があり教育委員会が指定した学校以外へ変更する制度。ただし学校運営上支障のおそれがある場合は制限」とし、承認基準の表も提示。(*10)
- 府中市:「指定校を変更せざるを得ない事情がある場合、基準に基づく審査で相当と認められ、受入校にも支障がない場合に限り変更可」と明記。(*11)
✔ 自治体をまたいで通う「区域外就学」の具体例
- 世田谷区:「区域外就学は、承諾基準に該当し、さらに学校運営・施設の受入状況から特に支障がないと認められる場合に承諾(制限校は除外)」と明示。(*12)
- 台東区:「他自治体から台東区の学校に通う制度。ただし学校運営上支障をきたす恐れがある場合は制限」「教育委員会が認める理由がない場合は応じられない」と明記。(*13)
- つくば市:区域外就学の許可基準に合わせて、教室数の余裕や将来推計により“受入れを制限する学校を指定していると明記(具体的な制限校名も列挙)。(*14)
注意点
いずれの自治体の事例を見ても、重要なのは受け入れ側の余裕の有無です。
人気校や教室にスペース的な余裕のない学校校では、受け入れ制限や抽選が行われ、妥当な理由があっても人数上の上限で不承認になることがあります。
実務的には通学費が家庭負担になりがちで、通学手段(自転車など)の許可ルールにも地域差があります。希望校だけに依存せず、代替案(第2志望校や第3志望校など)を持つことが大切です。
当てはまる人(例)
- 通学経路の安全上の不安があり、別ルートの学校を希望したい
- 健康・発達上の配慮やいじめ・不登校への対応として環境を変えたい
- 転居予定があるため、先に新しい生活圏に合わせたい
- 兄弟姉妹と同じ学校にそろえたい
- 親の通勤や送り迎えの都合に合わせて、職場・学童・祖父母宅の近くの学校にしたい
パターン3. 公私間・国私立との行き来(公立↔私立/国立)
パターン3は、公立から私立、または国立へ、あるいは私立・国立から公立へ小学校を切り替えるパターンです。私立・国立は各校が受け入れ基準や時期を定めるため、転・編入の募集がある学期/学年に限り受け入れが行われます。
一方、公立へ戻る場合は、基本的に住所地の通学区域にしたがって就学先を定めることになります。
公私間の行き来は制度上可能ですが、学校文化・教育方針・評価のやり方が異なることが多く、子どもの相性や家庭の価値観と照らして慎重に見極めることが大切です。
注意点
私立・国立側は、空き状況・学力到達・学校方針との相性を見て受け入れを判断します。選抜や面談、提出書類(在学状況・成績・健康情報など)が求められるのが一般的で、希望時期に枠がないこともあり得ます。
✔例
- 東京学芸大学附属大泉小学校:児童面接/筆記(日本語の会話力、国語・算数の基礎、作文)+保護者面接。(*15)
- 私立立教小学校:学校の教育方針(キリスト教主義)も要項冒頭に明記。(*16)
公立へ戻る場合は、教科書会社の違いや宿題の量、連絡体制、校則(持ち物の色・形など)まで含めた学校間でのギャップに注意が必要です。
当てはまる人(例)
- 特色ある教育方針(探究・英語・宗教・芸術など)を重視して私立・国立を検討したい
- 現在の私立・国立が生活や費用の面で合わず、公立へ戻したい
- 海外や他地域から戻ってきて、私立・国立への“途中合流(編入)”を考えている
- 通学時間を短縮/家庭の事情に合わせて学校文化を選び直す必要がある
パターン4. その他
パターン4は、ここまで紹介した1~3には当てはまらない事情に基づいて在籍先を調整するパターンです。
たとえば、海外赴任からの帰国や長期滞在の終了、医療的ケアや長期入院、いじめ・不登校への対応、災害や校舎建替えによる一時的な受け入れなどが含まれます。以下は例外的な転校のケースです。
- 日本語指導が必要な児童生徒は近年増加(2023年時点で全国6万9,123人、文科省公表を各紙が報道)。横浜市のように校内に「国際教室」を設置する学校がある自治体の場合、「その学校で学ばせたい」と希望する方もいるので、指定地区外就学(=指定校変更に相当)となる可能性がある。(*17)
- 病院に設置された特別支援学校の「病院訪問学級/院内分教室」で、入院中も学習を受けられる制度もある。(*18)
- 災害時は、住民票を移さず避難先の公立校に通える等、柔軟な受け入れを行う自治体もある。(*19)
注意点
判断はケースバイケースで、教育委員会・学校・医療・福祉の関係者が情報を共有して決める場面が多くなります。
重要なのは、子どもの状態や必要な配慮の記録(医師意見書・支援計画・相談記録)を整え、いつ・どこで・誰が・何を支援するかを明確化しておくことが重要です。
災害等の非常時には、書類要件の簡素化や臨時学区の設定など平時と異なる運用が行われるため、自治体からの公式発表に即して柔軟に合わせる姿勢が求められます。また、帰国児・外国につながる子どもの場合は、日本語指導や学習の“つなぎ”の有無が適応のカギになるため、受け皿(取り出し指導・支援員配置など)の有無を確認しておくと安心です。
当てはまる人(例)
- 海外からの帰国、または海外転出や長期滞在の開始・終了がある
- 医療的ケア・長期入院・療養で学びの継続に配慮が必要
- いじめ・不登校等で安全確保と段階的な復帰のために環境を調整したい
- 災害・校舎建替えなど地域事情で一時的な受け入れや学区見直しが起きる
*3 「転居予定地の通学区域の学校に、今から通うことはできますか?」金沢市
*8 「市内間で転居し学校区が変わるが、今までの学校に通学することはできますか。」こたえてコール 新潟市役所コールセンター
*10 「指定校変更について」台東区
*12 「区域外就学承諾基準」世田谷区
*13 「区域外就学について」台東区
*15 「令和7年度 国際学級 海外生活経験児童 9月編入学募集要項(第3~6学年対象)」東京学芸大学附属大泉小学校
*17 「国際教室での学習」生麦小学校
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
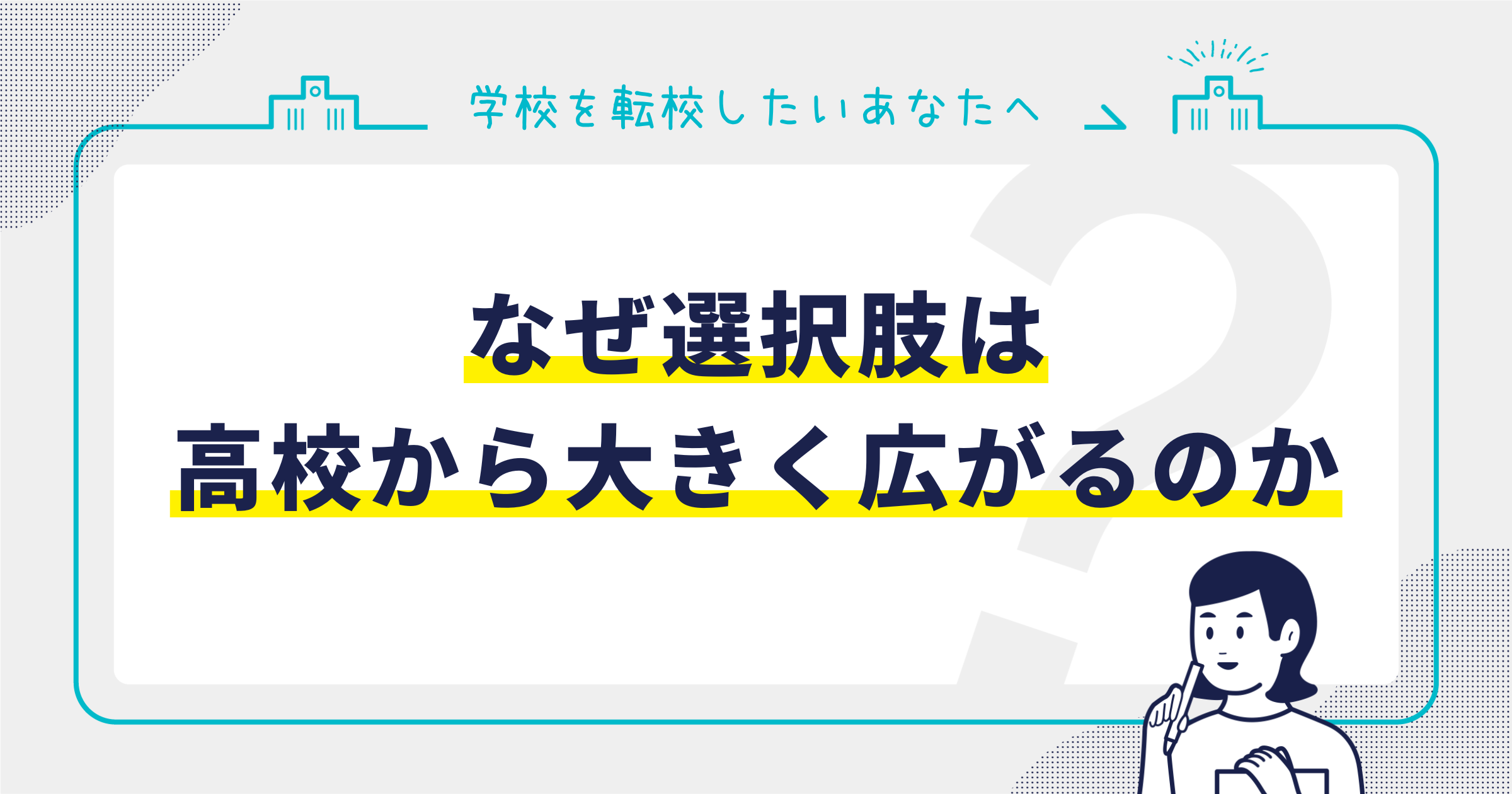
なぜ選択肢は高校から大きく広がるのか(義務教育と学区の仕組み)