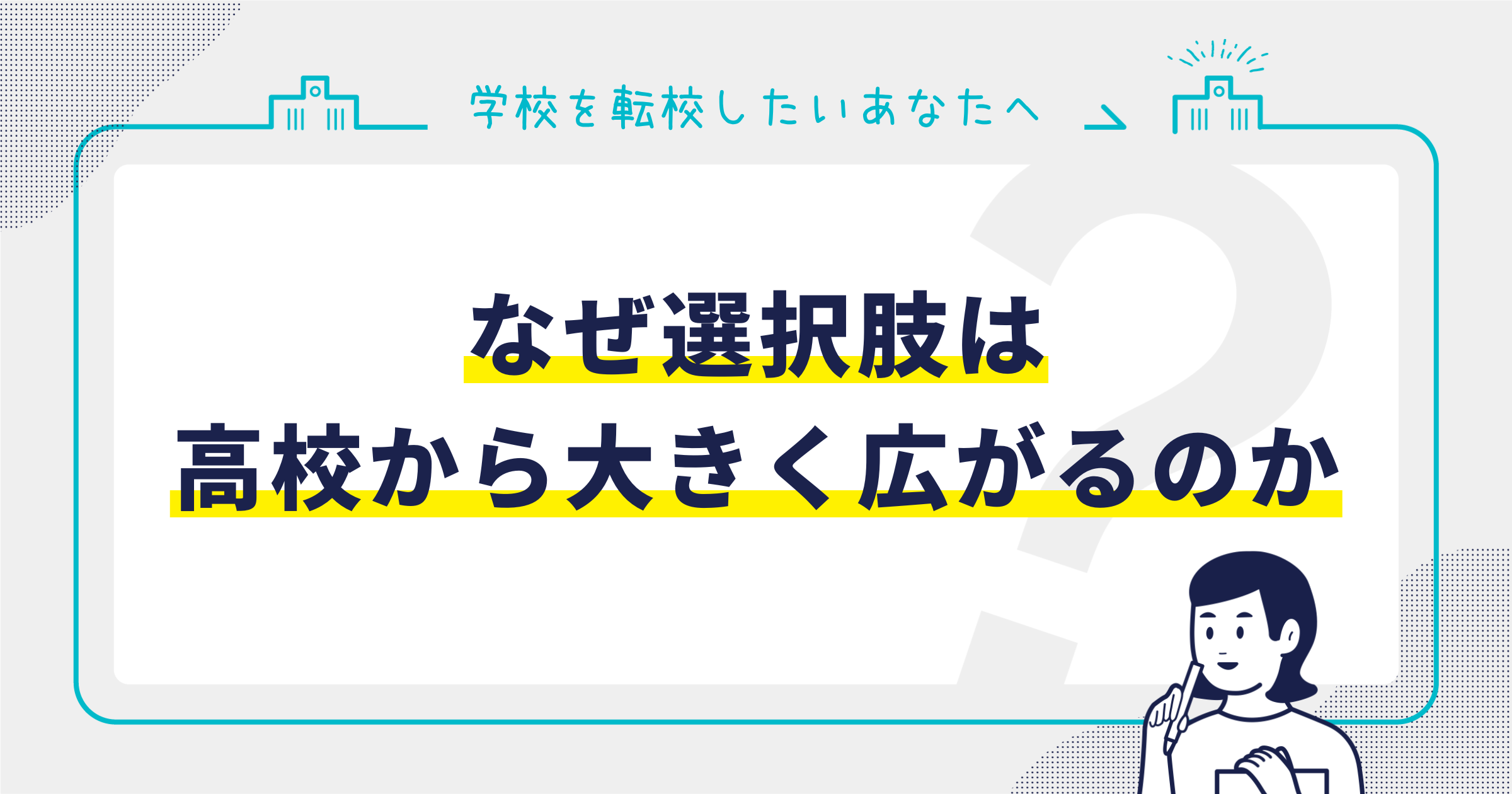「小中学校の転校はこんなに大変なのに、高校になったら一気に選べる学校が増えるのはなぜ?」
その理由は、義務教育と学区(通学区域)という2つの決まりにあります。ここを押さえると、なぜ中学校までは転校しにくく、高校から爆発的に選択肢が増えるのかがはっきり見えてきます。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、小中学校における転校の制約と、高校における選択肢が急増の背景について進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
義務教育の役割:誰も取り残さない「近くの学校」という原則
小学校・中学校は義務教育です。国は「すべての子どもに、生活圏内で、確実に教育を提供する」責任があり、教育委員会が住所にもとづいて”通う学校(指定校)”を決めます。(*1)
この「指定校」は、教室数・通学距離・通学の安全性を見込んで決定されるようです。例えば、横浜市では通学区域の決定について下記のように述べています。(*2)
通学区域設定については「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、「学校規模」「通学距離」「通学安全」を基本としつつ、「地域コミュニティとの関係」や「行政区」、「小学校・中学校の通学区域」を総合的に配慮して設定し、小学校では片道おおむね2km以内、中学校では片道おおむね3km以内を望ましい通学距離としています。
つまり自治体は「定員と通学」を中心に学校運営を組み立てているので、学年の途中に一度に多くの転入があると、教室や先生の数が足りなくなりやすいため、受け入れに限りがあります。
まとめると次のとおりです。
- 義務教育=国・自治体が受け入れる責任を持つ
- そのため、学区で割り振り、設備・人員を計画配置
- 結果として、自由な学校選択は難しい
学区制の仕組み:小中学校の「通える範囲」を先に決める
子どもの住所に基づいて「通学区域」を定め、各家庭に指定校を決める仕組みが学区制です。
例外的に、同一自治体内での指定校変更(通学の安全・きょうだい在籍・健康上の配慮など)や、自治体をまたぐ区域外就学が認められる仕組みはありますが、どちらも「申請→教育委員会が許可するか判断」という仕組みです。
✔区域外就学が認められる自治体の例
- 静岡市:「特別な事情」に該当すれば保護者の申立てにより教育委員会が変更を認めると明記(*3)
- 世田谷区:区域外就学の承諾基準を公開。「学校運営上や施設の受入状況に支障がないと認めるとき承諾」と明記。(*4)
- 台東区:他の自治体(原則東京23区内)から台東区の学校に通学する制度あり。ただし「教育委員会が認める理由がない場合は応じられない」。また「学校運営上支障がある場合は制限」と記載。(*5)
- 奈良市:就学する学校の変更及び区域外就学の審査基準に該当する「特別な事由」があれば許可と明記。(*6)
- 廿日市市(広島):指定学校の変更許可基準(転居・健康・配慮事項など)を公開。教育委員会へ申立てを行い、許可する決まり。(*7)
希望者が多い学校や教室が足りない学校では、受け入れ人数に上限を設けたり、希望者が上限を超えたら“公開抽選”で決めたりします。(*8)
例えば、東京都調布市では中学校選択制について「学区域外の学校を希望した方が入学できるのは、それぞれの学校の受入れ可能人数までとなります。それを超えた場合は公開抽選となります。」との記載があります。
小中学校において転校のハードルが高い理由は、学校側のキャパシティや通学距離などが主です。義務教育である以上、「すべての子どもに、生活圏内で、確実に教育を提供する」ということが前提での仕組みとなっているため、簡単に通う学校を変えることができないのです。
なぜ高校から選択肢が爆発的に増えるのか
一方、高校(全日・定時・通信)は義務教育ではありません(就学支援制度は厚くなりましたが、”就学させる義務”ではない)。そのため、家庭が学校を選び、学校は入学の基準に合うかを見て受け入れます(入試や選考)。
高校から学校の選択肢は爆発的に増える。直感的に理解している方も多いと思いますが、ここからは、高校から選択肢が増える理由を、順を追ってお伝えしていきます。
高校は“通える範囲”が広い
まず、高校の通学区域は都道府県単位で運用され、多くの地域で学区を緩和したり、学校によっては広域募集を行ったりしています。小中学校ほど住所で縛られません。
例えば大阪府では2014年度の入試から府立学校の学区を撤廃(*9)。同じく富山県でも2024年度に4つあった学区を廃止し、全県一区としています。(*10)
このように、高校では学区が緩くなって、進学先が広くなっているのです。
高校は“通い方”を選べる
全日制高校だけでなく、通信制高校・定時制高校のように、時間・場所・ペースの違う通い方が増加してきました。
前記事(データで見る「転校」の今)の通り、2024年度に通信制高校の生徒数が29万人超と過去最多。これまでは全日制高校への進学を前提としていた方も、通信制高校など他の選択肢を入れやすくなりました。
その他に、高校は転編入試験や編入枠を設ける学校が多く転校しやすいことなども、選択肢が増えたと感じる要因だと言えます。
つまり高校は、
- 住所ではなく、本人の選択と出願で通う学校が決められる
- 通信制高校や定時制高校など、多様な通い方が制度として並列
- 学期の終わりなどに“転学・編入の募集”を出す高校が多く、選び直しやすい
この3点により、高校から選択肢が爆発的に増えるように感じるのです。
小中学校は、「義務教育×学区制」という“守りの仕組み”で運用されます。だからこそ、転校は例外処理になりがちで、動きづらい。
一方で高校は、自分で通う高校を選ぶ、合わなければ他の高校に変える“攻めの仕組み”が基本。通い方も学び方も分野も、組み合わせ次第で大きく広がります。
*1 「学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条」 文部科学省
*2 「小学校の通学区域を見直してください」「市民の声」の公表 横浜市 市民局 広聴相談局
*7 「指定学校変更許可基準」 廿日市市子育て支援サイト「はついく」
*8 「指定校変更と区域外就学」東京都北区役所 / 「中学校選択制に関するQ&A」 調布市役所 など
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
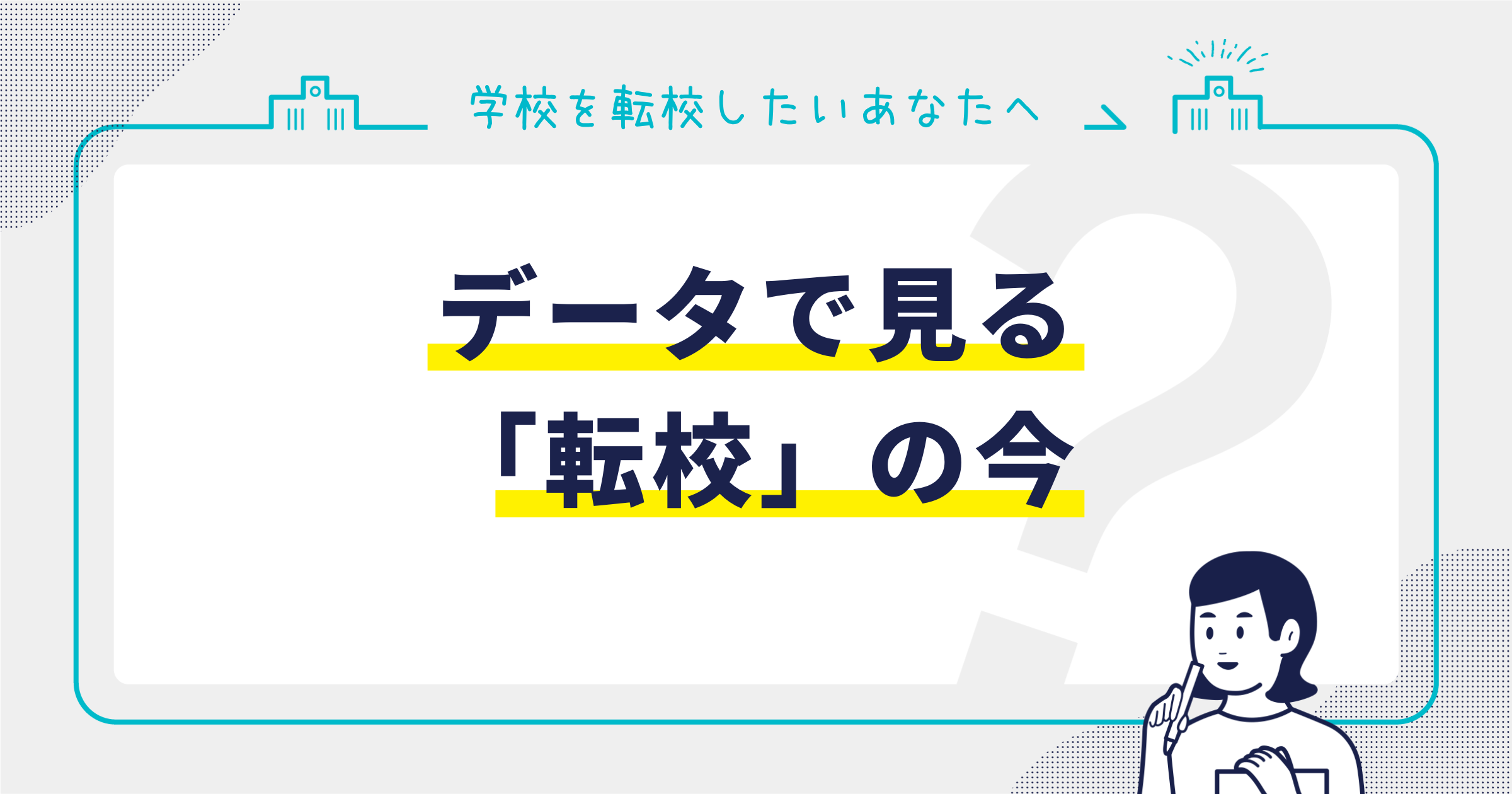
データで見る「転校」の今
次の記事
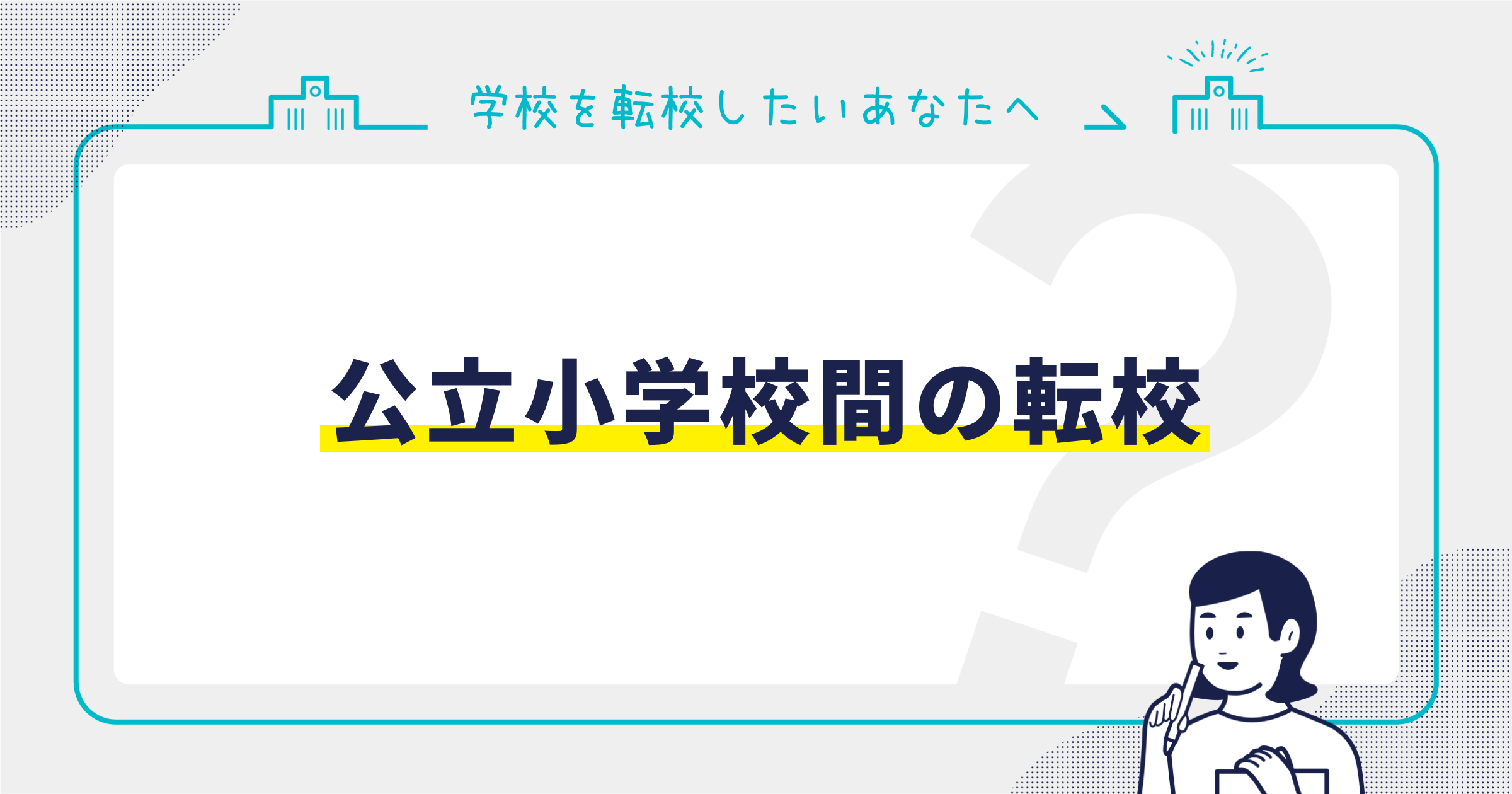
公立小学校間の転校