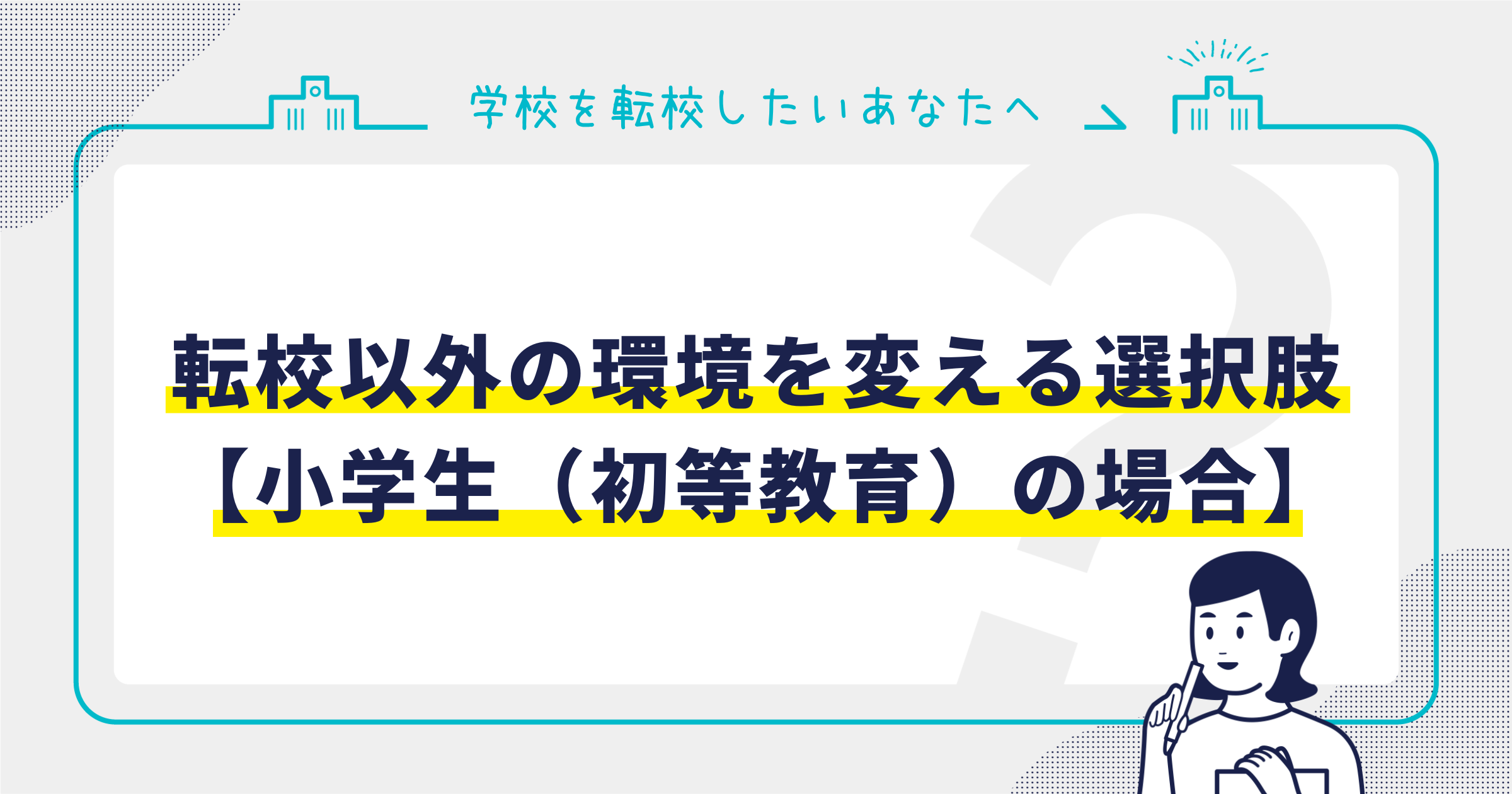「転校せずに学ぶ環境を変えることはできないだろうか」
このように考える方もいるでしょう。
実は、同じ学校のままでも、学ぶ「場所・時間・人」の組み合わせを変えて子どもに合う環境を作ることはできます。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、転校以外で学ぶ環境を変える選択肢を8パターンに整理し、それぞれ「何ができるのか/想定されている利用者/注意点」について、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
パターン1. 通級による指導(いわゆる“取り出し授業”)
パターン1は、通級による指導です。通常学級に在籍しながら、週の一部時間だけ別室(通級指導教室)で、子どもの困り感(読む書く・計算・行動面など)に応じた個別支援を受けられます。「取り出し授業」と呼ばれたりします。制度上は自校通級・他校通級・巡回の3形態があります。(*1)
2023年度には通級指導を受けた児童が全国で20万人を超えて過去最多を記録。この結果を受けて、通級指導の充実度を高めるよう文部科学省が呼びかけを行いました。(*2)
想定されている利用者
- 授業の大半はクラスで学べるが、一部で継続的な支援が必要
- 学習面/行動面の特性によるつまずきがある
- 環境を大きく変えず、ピンポイントに支援を受けたい
注意点
通級指導の対象となるかどうかの判断は校長を中心に行われ、設置・受け入れ状況は自治体で差があります。(*3)
パターン2. 特別支援学級(学校内の別学級)
パターン2は、特別支援学級です。在籍を特別支援学級に置き、少人数で個別化された教育課程で学びます。交流及び共同学習で通常学級の活動に参加することも可能。特別支援教育は法令上、全ての学校で実施されるべきと位置づけられています。
特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。(*4)
想定されている利用者
- 通常学級中心では、学びが進みにくい
- 通常学級よりも、個別サポート(人的環境・教室環境)がほしい
注意点
設置・在籍は地域差があり、学級の枠や校内体制は年度で変動。特別支援学級は1.6倍、児童生徒数は2.1倍に増加(*5)しているものの、校内体制については事前に確認したほうが良いでしょう。
パターン3. 校内教育支援センター(SSR/校内フリースクール)・別室登校
パターン3は、校内教育支援センターです。在籍校の中にある“別室”で、子どもにあったペースで登校・学習を進めます。「SSR(スペシャルサポートルーム)」や「校内フリースクール」、「別室登校」と呼ばれたりします。
担任・養護・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等と連携し、復帰や次の学びへつなげます。国も設置促進を打ち出しています。(*6)
想定されている利用者
- 教室に通うストレスが高く、まずは校内で安心できるスペースがほしい
- 教室復帰/併用を視野に、継続的に調整したい
注意点
設置率は拡大中だが地域差あり(全国平均設置率 46.1% / 2024年時点)。入室条件や過ごし方は学校・教育委員会の方針で異なりますので事前に確認しましょう。
パターン4. 教育支援センター(適応指導教室)
パターン4は、教育支援センターです。自治体が設置する“学校外”の学びの場で、生活リズムの立て直し、学び直し、対人関係の練習を行い、生徒と学校、生徒と進路とをつなぐことを目指しています。「適応指導教室」と呼ばれたりします。
例えば、東京都世田谷区では「ほっとスクール」という教育支援センターを教育総合センター内に設置しています。
ほっとスクール(教育支援センター)は、心理的理由などにより不登校の状態にある児童・生徒が、体験活動やスポーツなどの集団生活を通して、社会性や協調性を育み自立心を養い、学校生活への復帰や自分らしい進路の実現をめざします。(*7)
想定されている利用者
- 教室・校内での生活が難しく、まずは学校外からリスタートしたい
- 進学・復帰・別ルートなど選択肢を対話しながら決めたい
注意点
在籍校との連絡・計画(成績評価・出欠扱い等)の取り決めが重要です。また、自治体により名称・運用・通所日数が異なります。
パターン5. 学びの多様化学校(旧・不登校特例校)
パターン5は、学びの多様化校です。文部科学大臣の指定により、始業時刻の柔軟化や体験・探究、遠隔学習の活用など“子どもの実態に合わせた特別の教育課程”(*8)で学べます。
もともとは「不登校特例校」という名称でしたが、2023年8月31日に「より子供たちの目線に立った相応しいものにする」ことがうたわれ、学びの多様化校という名称に変更されています。(*9)
✔学びの多様化学校での教育課程例(*10)
- 八王子市立高尾山学園小学部:総合的な学習において、「講座学習」として教科にとらわれない個々の関心・意欲に応じた体験的な授業内容を週4時間設定
- 東京シューレ江戸川小学校:「いろいろタイム」を教科として新設し、自然体験や文化体験等の体験活動を行う
- ろりぽっぷ学園小学校:一人一人の学習進度に合わせた学習を行う時間を充実させつつ、協働的な学びの時間を確保
想定されている利用者
- 通常の時間割や評価では力を出し切れない
- 特定の分野に強い興味がある
注意点
地域ごとに学校数・形態(本校型/分教室型等)が異なり、定員や募集学年も学校ごとに設定しているため、入学を希望する場合、まずは通える距離に学びの多様化学校があるか確認しましょう。
パターン6. フリースクール(民間の学び・居場所)
パターン6は、フリースクールです。民間が運営する学びの場で、子どものペースに合わせた活動や学習支援、多様な大人・同年代とのつながりを得られます。
学校外での学習の「出席扱い」や通学定期の適用は、一定要件のもとで制度的に認められています(在籍校との合意が前提)。(*11)
想定されている利用者
- 学校に戻る/戻らないを含む“中立の居場所”がほしい
- 多様な大人・同世代と安心して関われる場が必要
注意点
学びの質や方針は団体ごとに異なるため、見学・体験で相性確認を。出席扱いの判断・成績評価は在籍校と取り決める必要があります。
パターン7. ICT等を活用した在宅学習(オンライン参加・課題学習)
パターン7は、ICT等を活用した在宅学習です。不登校支援の枠組みの中で、オンラインやデジタル教材による学習、段階的な参加を組み合わせます。文部科学省は“誰一人取り残さない学びの保障”として、校内外の居場所・ICT活用を強化しています。
想定されている利用者
- 対面登校はハードルが高いが、学びは止めたくない
- 登校再開へ向けて、まずは家庭での勉強を開始したい
注意点
「出席にできるか」「成績はどう付けるか」は国の決まりがあります。学校と保護者で作る“支援シート”どおりに進め、記録を残して定期的に見直すことが大事です。
パターン8. 病院内学級・訪問教育(病弱特別支援)
パターン8は、病院内学級や訪問教育です。入院・療養中でも、病院内の分教室や訪問によって学びを継続できます。医療と教育の連携で、体調に合わせた教育課程を編成します。
✔利用の流れ(目安)
- 主治医・病棟の院内学級窓口に相談(入院が見込まれたら早めに)
- 保護者が申請(在籍校・教育委員会・特別支援学校と連絡)
- 学籍・健康上の配慮・学習計画を確認(主治医の許可を前提に開始)
- 退院時は復学支援(元の学校と指導計画を共有し、無理のない復帰を調整)
想定されている利用者
- 入院や長期療養により登校が難しい
- 復学への橋渡しも見据えて、無理なく学びを継続したい
注意点
病気療養児は増加傾向(*12)との調査もあり、病院内学級・訪問教育の活用は各地で整備途上です。必ずしも入院先で利用できるとは限らず、ICT教育など他の選択肢も視野に入れましょう。
*1 「通級による指導の充実の在り方について」文部科学省
*2 「通級指導の児童生徒、20万人超で過去最多に 文科省調査」教育新聞
*3 「障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)」文部科学省
*4 「参考資料12:特別支援教育の推進について(通知)」文部科学省
*5 「特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書」
*6 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策推進本部(第4回)安心して学べる魅力ある学校づくりの推進に向けた方向性等について議論」文部科学省
*7 「ほっとスクール「城山」「尾山台」「希望丘」(教育支援センター)」世田谷区
*9 「「不登校特例校」の新たな名称について(通知)」文部科学省
*10 「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」文部科学省
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
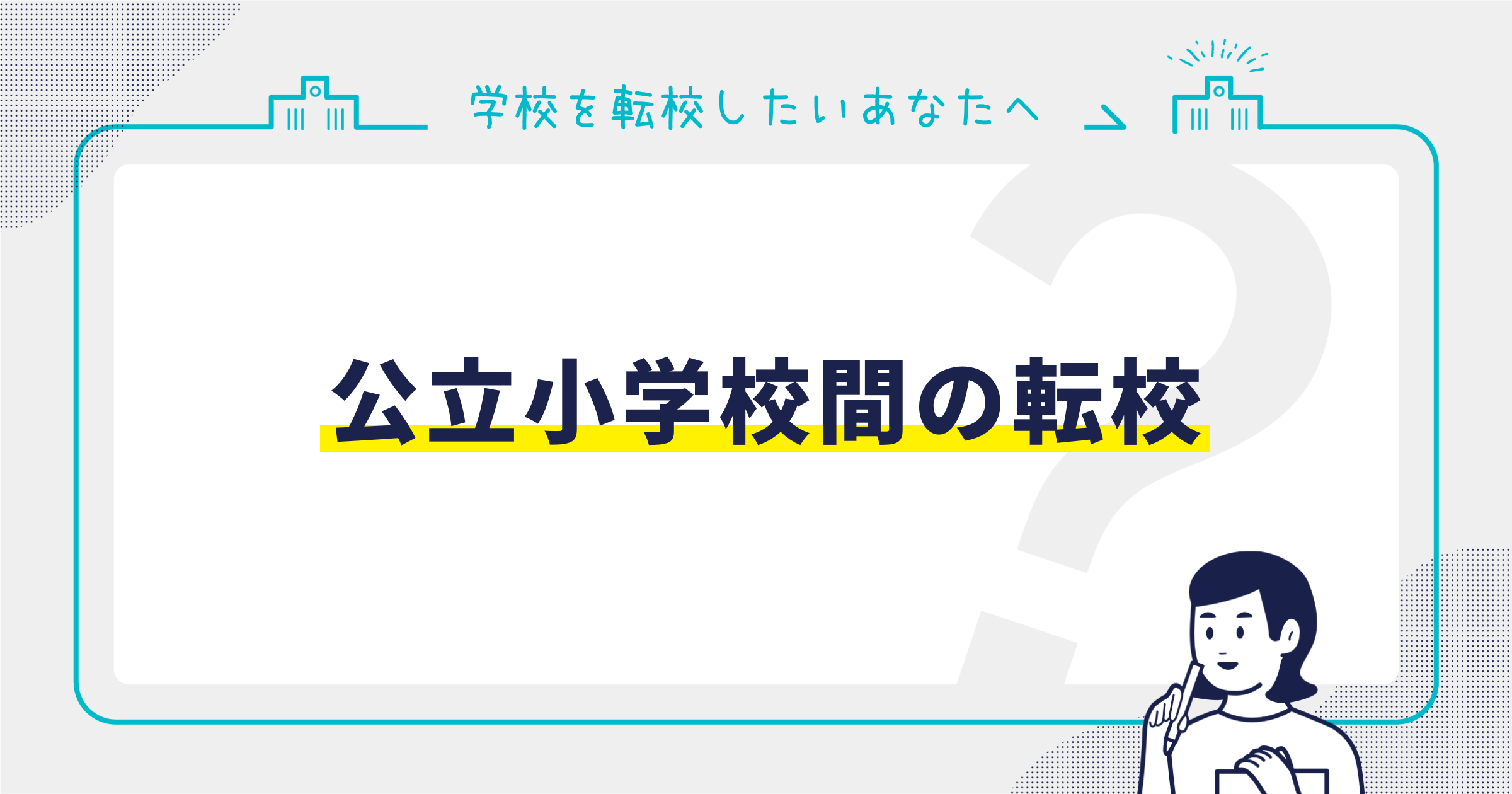
公立小学校間の転校