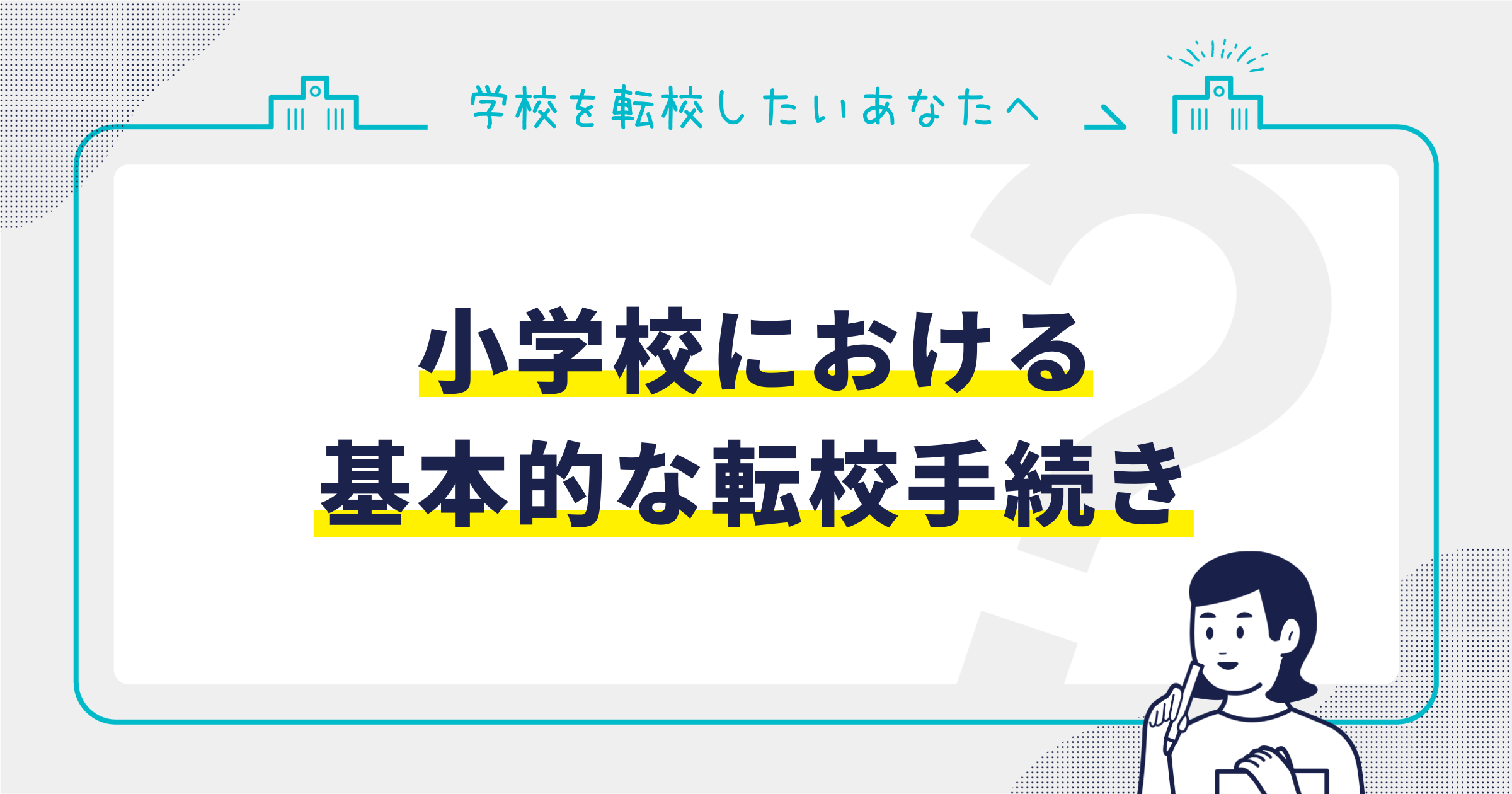引っ越しで住民票を動かす場合の転校は、全国どこでも大枠の流れは共通です。
多くの方にとって転校は、はじめてのこと。何から始めればいいかと迷わないように、「いつ・どこで・何をするか」を時系列で整理しながら、お伝えしていきます。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、小学校の基本的な転校手続き3ステップを進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
目次[非表示]
転校の3ステップ
- ステップ1. いまの学校に転出予定を連絡し、転出に必要な書類を受け取る。
- ステップ2. 市区町村で住民異動(転入/転居)を行い、就学先の通知を受け取る。
- ステップ3. 新しい学校へ書類を提出し、初登校日・持ち物・当面の生活の段取りを確認する。
この3ステップを押さえておけば、名称の違い(「転入学通知書」「就学通知書」「学校指定通知書」など)があっても迷いません。
ステップ1. 引っ越し前:いまの学校(旧校)でやること
退去日(最終登校日)の見通しが立ったタイミングで、まず担任と学校事務に「転出を予定しています」と伝えます。
学校側では、転校先での在籍・教科書配付の根拠となる在学証明書と教科書(教科用図書)給与証明書を準備します。
通知表などは転入先に引き継がれますが、配慮事項のメモ(アレルギー・服薬・学習面の配慮など)も、いまの学校の評価や支援を、転校先でも引き続き受けられるようにするために、同封してもらうとスムーズです。
併せて、貸与物の返却(タブレット・図書・名札等)や給食費・教材費の精算の段取りも確認しておきましょう。
「何を学校に置いて行くか/持ち帰るか」を整理することで、引っ越し前後の荷造り・荷解きがスムーズになります。
また、いまの学校(旧校)で受け取る書類は転校先へ持参する必要があるため、紛失しないように気をつけましょう。
✔いまの学校(旧校)で受け取る書類(*1東京都江戸川区の例)
- 在学証明書(在籍・学年・出欠等の証明)
- 教科用図書給与証明書(=教科書給与証明書)

在学証明書のレイアウト(*2)

教科用図書給与証明書のレイアウト(*3)
書類の名称は自治体によって変わる場合があります。
ステップ2. 引っ越し当日〜直後:役所でやること
引っ越しの届出(他市からの転入/同一市内の転居)を市区町村窓口で行うと、教育委員会が新住所に基づいて就学先(指定校)を決定し、転入学通知書(就学通知書/学校指定通知書)を交付します。

文科省指定の転入学通知書のレイアウト(*4)
これが新しい学校名・所在地・連絡先を明記した公式通知で、次の手続きの起点になります。本人確認書類・マイナンバー関連書類・印鑑など、自治体の案内に沿った持ち物もお忘れなく。
生活面では、学童(放課後児童クラブ)の空き状況・申込方法・開始時期が自治体ごとに大きく異なります。就学手続きと同時に子育て・放課後窓口で確認を。通学区域の地図や通学路の安全情報もここで入手できることが多いです。
なお、事情があって指定校以外を希望する場合(きょうだい在籍・通学安全・医療的配慮など)は、指定校変更や区域外就学という承認制の仕組みがあります。(詳細は公立小学校間の転校 パターン2. 住所変更なし(住民票はそのまま・通学先だけ変えたい)をお読みください。)
いずれも受入れ校の余裕や基準を満たす必要があるため、まずは学務担当に相談し、必要書類と審査の流れを確認してください(ここで扱っている内容は、あくまでも「指定校に転入する基本ルート」です)。
ステップ3. 新しい学校で:提出と初日の準備
転入先の学校に電話し、来校日時を決めたうえで以下の基本3点セットを持参または提出します。
- 在学証明書(旧校)
- 教科書給与証明書(旧校)
- 転入学通知書(就学通知書等)(行政)
書類の名称や細部運用は地域差がありますが「旧校の2通 、役所の1通を新校へ提出」という流れは全国共通です。
提出時は、初登校日・集合時刻・迎えの要否・通学路の確認、当面の時間割、連絡手段(連絡帳/アプリ/メール)の使い方、校内ルールと持ち物をまとめて確認しておきましょう。
上履き・名札・体育帽・体操服の型や色、筆箱や定規の指定、給食着の扱いなどは学校ごとに差があります。初日にすべてをそろえようとせず、学校の案内に合わせて優先度の高い物から順に準備すれば十分です。
給食のアレルギー対応は個別聞き取りと書類(医師意見等)が必要な場合があります。初日は弁当指示となるケースもあるため、事前に栄養教諭・養護教諭と情報共有を。
学童を利用する場合は、放課後の集合場所・迎えの動線・連絡方法を子どもと一緒に確認しておきます。
注意点:学期途中の転入
学期途中の転入では、これまでの学びとの“継ぎ目”をなめらかにすることが肝心です。
通知表の写しやノート・作品の写真、配慮メモがあると、評価の連続性や支援の引き継ぎがスムーズになります。
転校した最初の週は、行事・クラブ・課外の参加を詰め込みすぎず、生活リズムを整えることを最優先に。登下校の安全確認は保護者同伴で数回行い、危険箇所を一緒にチェックしておくと安心です。
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
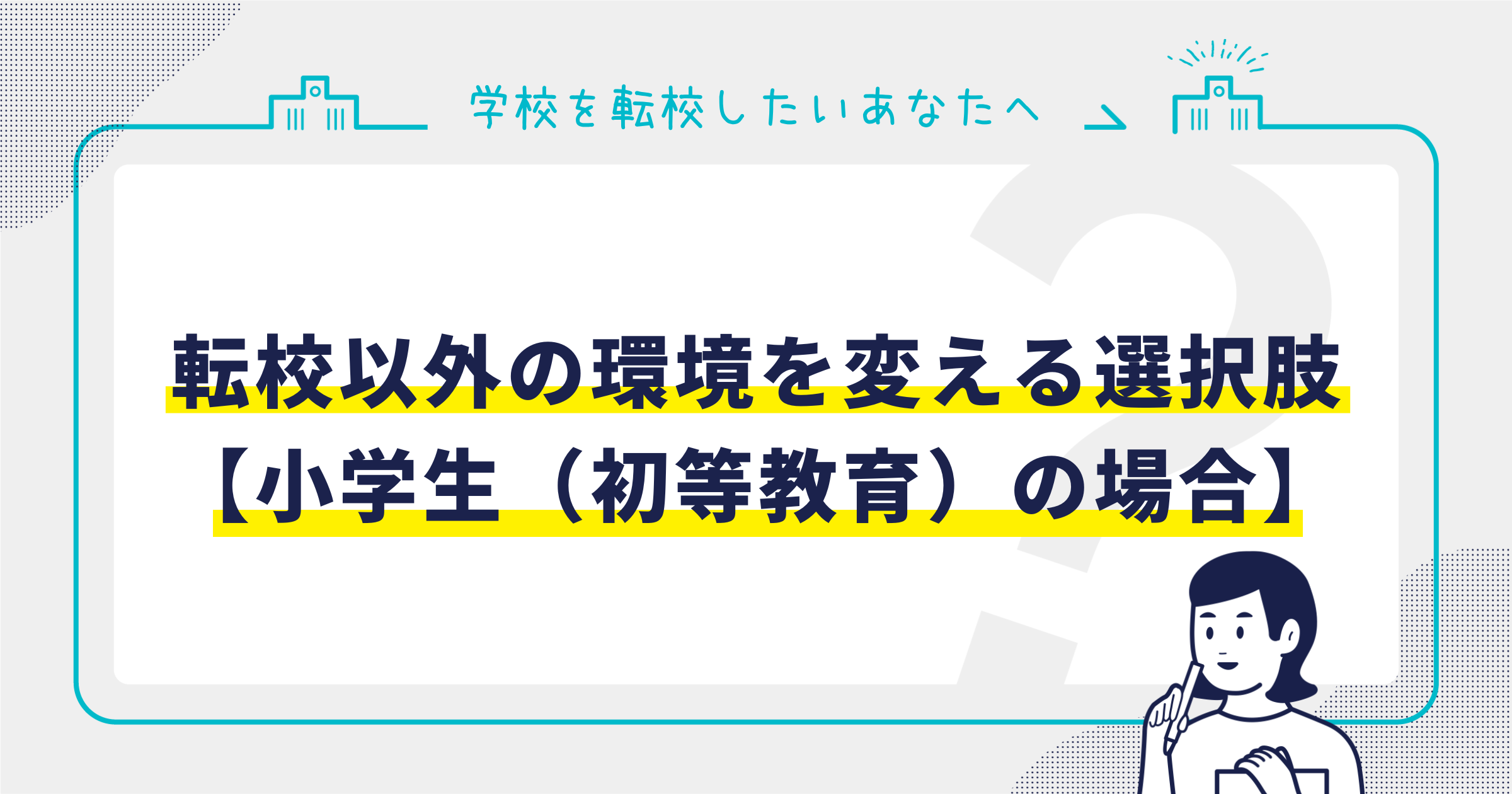
転校以外の環境を変える選択肢【小学生(初等教育)の場合】