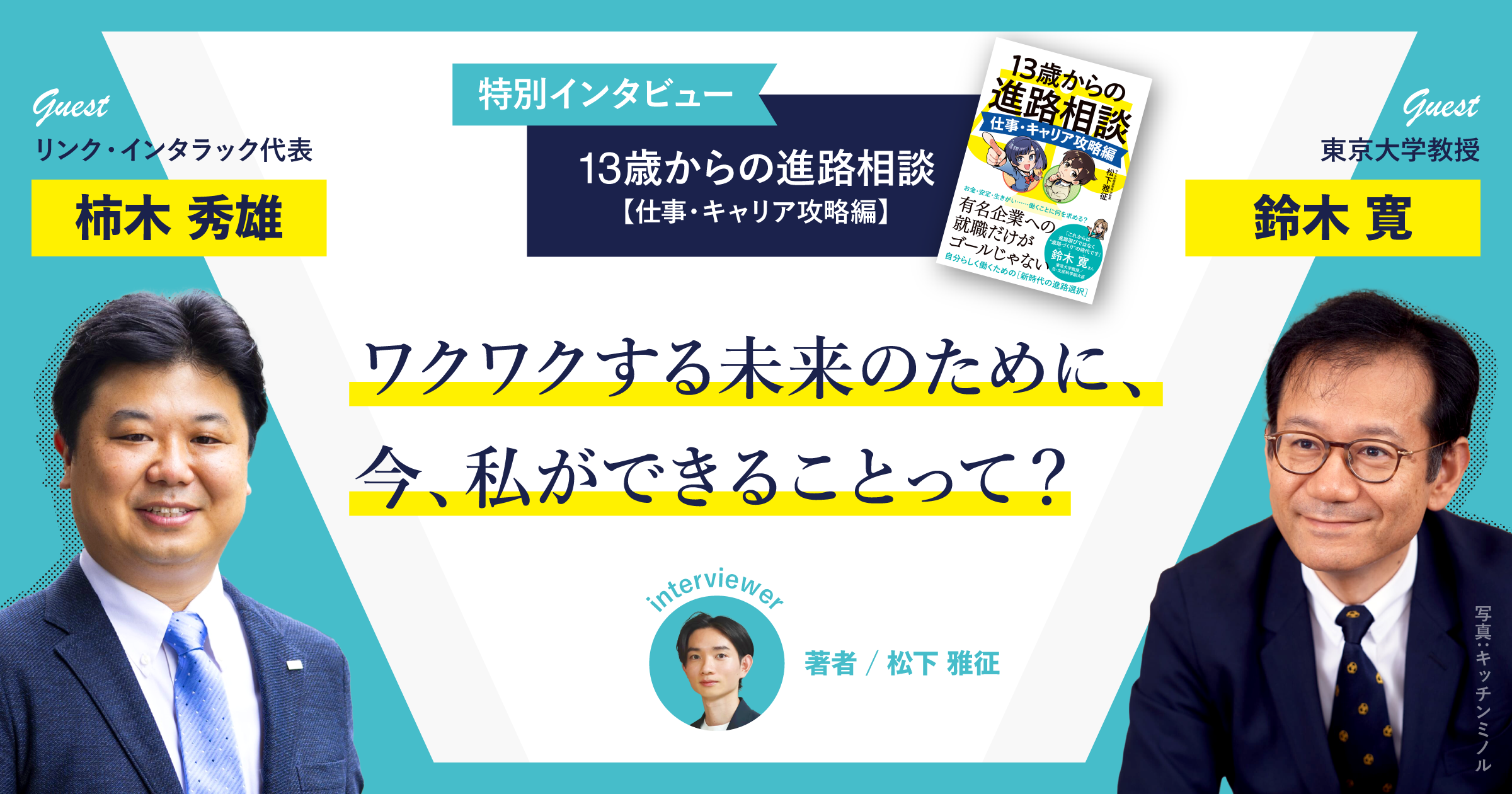記事を読むのにかかる時間 3分
人工知能(AI)の登場、進むグローバル化、国際情勢や社会問題の複雑化など、私たちを取り巻く環境は毎日のように変化しています。
そんな中、子どもたちがこれから生きていく時代は、大人の「当たり前」が通用しないかもしれません。ですが、心配しすぎる必要はありません。
子どもたちは新しい時代を切り拓き、そのために必要な力を身につける大きな可能性をもっているからです。
今回は、政治家や官僚として日本の教育政策に携わり、学習指導要領の改訂や40年ぶりの大学入学制度改革に尽力した“すずかん先生”こと鈴木寛さんと、公立学校へのALT(外国語指導助手)配置やグローバル人材教育を手がける株式会社リンク・インタラックの代表取締役社長・柿木秀雄さんに、「子どもたちがこれからの時代に身につけたい力」と「それを育むために大人ができること」についてお話いただきます。聞き手は、書籍『13歳の進路相談』の著者・松下 雅征です。

【鈴木寛(すずき かん)さんは、こんな人】
|
1964年生まれ。東京大学法学部を卒業後、官僚や参議院議員、文部科学副大臣、文部科学大臣補佐官とさまざまな立場から教育政策に従事。現在は東京大学、慶應義塾大学で教壇に立ち、「人づくり」「次代の社会づくり」に関与している。1995年からスタートした私塾「すずかんゼミ」は、これまでに1,000人を超える卒業生がいる。通称「すずかん先生」。
|

【柿木秀雄(かきのき ひでお)さんは、こんな人】
|
1984年生まれ。東京大学大学院(地球システム工学)終了後、組織人事コンサルティング企業、学習塾代表取締役、自治体教育委員など、さまざまな立場から組織創りや人創りに従事。現在は小・中・高等学校を対象とした、ALT(外国語指導助手)の配置事業や企業のグローバル人材育成事業などを行う、株式会社リンク・インタラックの代表取締役社長。
|
進路は選ぶのではなく、自分でつくる時代
松下 中学生や高校生のなかには、「自分の進路がわからない」と悩む人も多いです。すずかん先生や柿木先生は、この悩みをどうお考えですか。
鈴木 これからの進路は、選ぶのでなく、自分でつくっていくものです。今までは、「良い進路」と呼ばれるものがありましたが、そもそも2つとして同じ進路はありません。
自分にとって良い進路か?が大事。自分の意志で、まわりの人たちの協力を得ながら進路をつくっていくことが大切だと思いますね。
なぜなら、これからどんどん予想がつかない時代になっていくから。読者の皆さんのなかにも「将来、こんな仕事に就きたいな」と思っている人がいるかもしれません。
けれど、人工知能(AI)が人間の知能を上回っていく「シンギュラリティ」が起こり、AIやロボットが人間の代わりに働くようになると、今ある仕事の半分ぐらいが将来なくなってしまうだろうと言われています。
でも、13歳のみなさんが社会に出ていく頃には、今は存在しない仕事がどんどん生まれてくるはずです。
松下 「予想ができない時代」がやってくる。そのことにワクワクしている人も、ちょっと不安だなと感じている人もいるかもしれません。
鈴木 私は「子どもも大人も、一緒に”幸せってなんだろう”と考え直してみようよ」と提案しています。今までは、物が増えたり、経済的に豊かになることが幸せだと考えられてきました。それも大事なことだけど、それだけが幸せではありません。
SDGsやウェルビーイングという言葉があるように、幸せにはいろいろな形があるんです。「自分らしい幸せってなんだろう」を考えるためには、好きなことを探究したり、挑戦したりといった力が必要になってきます。
柿木 これからは、海外の人たちと関わる機会がもっと増えていきます。今13歳のみなさんには、ちょっとイメージしにくいかもしれないけれど、経済や環境、社会、政治など、あらゆる分野が世界中の国々と深く結びついています。
たとえば環境問題は、日本だけで解決できませんよね。技術が進んで、物理的な距離を飛び越して、世界の人とコミュニケーションができるようになり、ひとつの世界になっていくでしょう。
そうすると、多様な視点や異なる価値観を持つ人たちと協力することが当たり前になり、複雑な問題を一緒に解決しようとする時代になります。話題の「メタバース」のように、仮想空間で国や地域に縛られずに生活できる世界が出てくるかもしれません。
夢中力と柔軟性が未来を拓く
松下 では、そのような新しい時代に、子どもたちはどのような力を身につけておくといいのでしょうか。
鈴木 「夢中になる力」、つまり「夢中力」ですね。日本の子どもたちって、15歳くらいまでは、基礎学力がOECDのなかでトップクラスです。でも、いろいろなことに好奇心を持って熱中し、深く探究していく力が、まだ足りないように感じています。
実は、小学校へ入学する前の子どもたちは、夢中力にあふれているんですよ。それを親がつい、邪魔しちゃうんです。たとえば、何かに集中しているときに「もうやめなさい」って中断させられた経験、ありませんか?
そうやって、繰り返し邪魔をされると、小学校の高学年ぐらいになって「もういいや」ってなってしまうんです。だから私は、保護者に「子どもがフロー状態、つまり夢中になっているときは、ただ見守りましょう。口を出して止めさせないで」と伝えています。
「今、夢中になれるものがないな」と思う子がいたら、夢中な人たちが集まっている場に行ってほしいですね。夢中な人がいる場所に行くと、そのエネルギーに触れ、自然と自分もワクワクしてきます。
もちろん、興味がわかなくてもいい。なるべくたくさん、夢中力を持つ人がいる場所へ行くなかで、「いいなぁ」「自分もワクワクしてきたな」と思えるものがひとつでも見つかれば、自分の夢中力を取り戻すきっかけになります。
松下 自分が何かに夢中になるんじゃなくて、夢中な人がいる場所へ行くという考え方は、おもしろいですね。
たとえば、自分はサッカーをやってみたことがなくても、サッカーを応援している人たちの輪に入ったら、ワクワクすることもあります。
では柿木さんは、新しい時代にはどんな力が大切だと思いますか?
柿木 自分で考え、行動し、答えが決まっていない問題に挑む力、そして柔軟性が必要だと思います。これからの社会は複雑な問題が増えて、正解がひとつに決まらないことが多くなります。だから一つのやり方にとらわれず、その状況に合わせて考え方やアプローチを変えられる柔軟性が求められます。
さらに、国際的な視点も欠かせません。さきほどもお話したように、これからは国や言葉、考え方が違う人たちと協力して問題を解決する時代になっていくので、相手を思いやり、共感する力が重要になります。
子どものうちは、同じような環境の仲間と過ごすことが多いかもしれません。でも、英語の授業ではALT(外国人指導助手)の先生がいますよね? その先生は年齢、国、宗教や価値観がみなさんとは違うはず。
たとえば「学校での過ごし方」一つとっても、日本とは違う体験をしているんです。次の英語の時間に、ALTの先生と議論してみてください。きっと「答えがひとつじゃない問題」に触れることができるはずです。
松下 先生と議論するなんて、考えたことありませんでした。面白そうですね!
柿木 学校や塾では、先生から知識を教えてもらうという、一方的な授業の形が多いですよね。そうすると、自分で考えたり、柔軟な見方をしたりするチャンスが少なくなってしまいます。
すずかん先生は「熟議(※)」という言葉をよく使われますが、子どもたちが納得いくまで話し合える時間や場所が本当に大切だと思います。大人はそのとき、口を挟まずに見守ってほしいです。
※熟議(じゅくぎ):ある問題に対して関心を持つ当事者が、熟慮し議論することにより、問題を共有し、解決策を見いだすというもの(参照:鈴木寛公式サイト)
松下 大人が見守ることで、子どもたちは安心して自分の意見を言えますよね。
柿木 そうですね。子どもたちが安心して話し合いができるような環境を整えたいです。話し合いがヒートアップして、言葉が荒くなったりケンカになったりすることもあるかもしれません。そんなときは、大人が「もう少しこう伝えてみようか」と声をかけることで、落ち着いて話せる空気をつくれます。
みんなが安心して発言できる「安心インフラ」があれば、今まで意見を言うのをためらっていた子も、勇気を出せるようになると思います。
自分だけの自由な時間を過ごそう
松下 では、夢中になれる力や、答えのない問題に挑む力、柔軟性や共感する力を身につけるためには、具体的にどんなことができるでしょうか?
鈴木 まずは、自分が自由になれる時間や場所をつくってみましょう。日本の子どもたちは、習いごとに塾にと忙しくて、ほとんど余白がないんです。それに、地域や家のなかにも、「何をしてもいいんだよ」という本当に自由な場所や空間はなかなかありませんよね。
自分の部屋なのに、壁に落書きしたり、散らかしていたらお母さんに怒られるでしょう?でも自由に作ったものをそのまま残しておくと、新しいアイディアがわいてきたり、クリエイティビティが刺激されたりするんですよ。
だからこそ、意識的に自由になれる時間や空間を作っていかなきゃいけない。子どもはもともと元気と好奇心を持っているので、ゆとりがあればその力が戻ってきます。元気を取り戻して、子どもは自由にいろんなことを楽しめますから。しっかり寝て、自由な時間に好きなことをやってみる。それだけで、夢中力が再びわいてきますよ。
柿木 また、いろいろな人とつながることも大切です。たとえば学校の中で、違う学年の人や先生、地域の大人たちと話し合う機会をつくる。オンラインなら、全国や世界の同年代、社会で活躍している人たちともつながれます。自分と違う背景を持つ人たちと交流することで、共感力や柔軟性、そして自分の考えを伝える力が育まれます。
それでも、はじめの一歩を踏み出せない子もいますよね。失敗を怖がって、完璧にできないと動けない子が多い気がします。「間違えたらどうしよう」って考えちゃうんです。でも、英語で言いたいことがすぐ言えなくても、とりあえず日本語で気持ちを伝えようとしただけでOK。その気持ちが出てきたこと自体をほめましょう。小さなステップを踏むなかで、少しずつ自信がついていきます。
「はじめから完璧じゃなくていいんだよ」と、まわりの大人も声をかけてほしいですね。たとえば、英語を話せなくても、まずは「こう言いたいんだけど…」と伝えようとする。その気持ちだけでも前進です。そのあと、まわりが「英語で言うとこうなるよ」と教えてあげればいい。
ステップを低くして、登りやすい階段をつくれば、「苦手だな、怖いな」と思っていたことも、少しずつクリアできるはずです。大人やまわりの人が、低い階段からチャレンジできるようにサポートすることで、子どもたちは安心して一歩を踏み出せます。
大人に本音を伝えてほしい
松下 子どもたちが大人に本当の気持ちを伝えたいとき、どんなふうに言葉にすればいいでしょうか? 「恥ずかしい」「うまく話せない」のように、伝えることに難しさを感じる子も多いと思いますが、鈴木さんはどうアドバイスしますか?
鈴木 自分が「嫌だ」と思うことは「嫌だ」と伝え、「やってみたい!」と思うことは「やりたい」と声に出してみましょう。もちろん、親や先生に反対されることもあるかもしれませんが、まずは自分の思いを言葉にしてみることが大切です。
うまく言えなくてもいいんです。とりあえず伝えてみる。口で言いづらければ、文章に書いて手紙やメッセージアプリで送ってもOK。
大事なのは、つらいときや困っているときにSOSを出せること。小学校の高学年から中学生の時期は、しんどいことも多いと思います。でも、がまんして自分一人で抱えこまず、大人に伝えてほしいです。
松下 大人だって、子どもの気持ちをすべて理解できているわけじゃありません。子どもから伝えてもらえれば、大人も協力しやすくなります。
柿木 遠慮をしないで、本音をぶつけてほしいですね。それが難しければ、話す相手を変えてみる方法もあります。担任の先生じゃなくても、好きな教科の先生や信頼できる先輩など、話しやすい人を選んでみるといいですよ。違う立場や視点の人と話すことで、新しいアイデアやアドバイスがもらえると思います。
13歳の未来には、ワクワクが待っている
松下 最後に、読者のみなさんへメッセージをお願いします。
 鈴木
鈴木
|
みなさんには、好きなことをとことん大事にしてほしいです。進路や仕事って、「好きなこと」を実現するためにあるものだと思います。好きなことが仕事やライフワークになるほど、楽しい人生はありません。
でも、13歳の時点で好きなことを見つけるのは難しいかもしれないし、まわりの環境から「好き」を抑えられちゃっていることもあるかもしれません。だから、18歳くらいまでの間に、何か一つでも「これだ!」と思える好きなことを見つけてほしいんです。 そのためには、思いきり好きなことをやっている人生の先輩たちと出会ってみたり、そういう人たちが集まる場所に行ってみたりする。「つまみ食い」するように、いろんな出会い、経験をしてほしいですね。 |
 柿木
柿木
|
私は今40歳ですが、この40年間で社会はものすごく変わりました。13歳の子どもたちが40歳を迎えるころには、「やろうと思ってたことができるようになった」という変化がもっとすごいスピードで進んでいるはずです。
そんな未来は、きっと楽しくてワクワクする世界だと私は信じています。その中で「好きなこと」を大切にすれば、人生はさらに充実します。社会の基盤はコンピューターやロボットが支えてくれる時代になっていくかもしれません。そうなれば、「生きる意味」を見つけるには好きなことに全力で打ちこむことが大事になってきます。そして、その「好き」が誰かに共感されたり、誰かの役に立ったりする時代がやってくるでしょう。 そして、人と人のつながりを大切にしてください。これからは、驚くほど多くの人達と関わり合う時代になると思います。いろんな考え方を持つ人たちと出会い、それぞれの考えを聞き合いながら、自分も相手も気持ちよく生きていける環境をつくれる人になってほしいです。 |
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
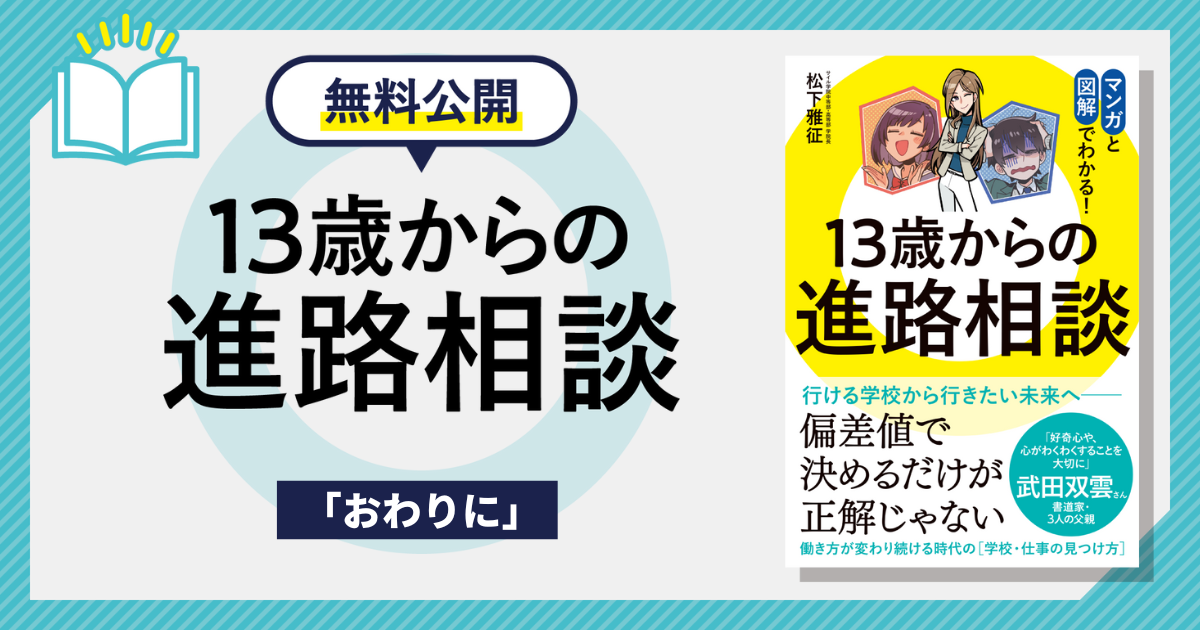
【無料公開】書籍「13歳からの進路相談」おわりに
次の記事
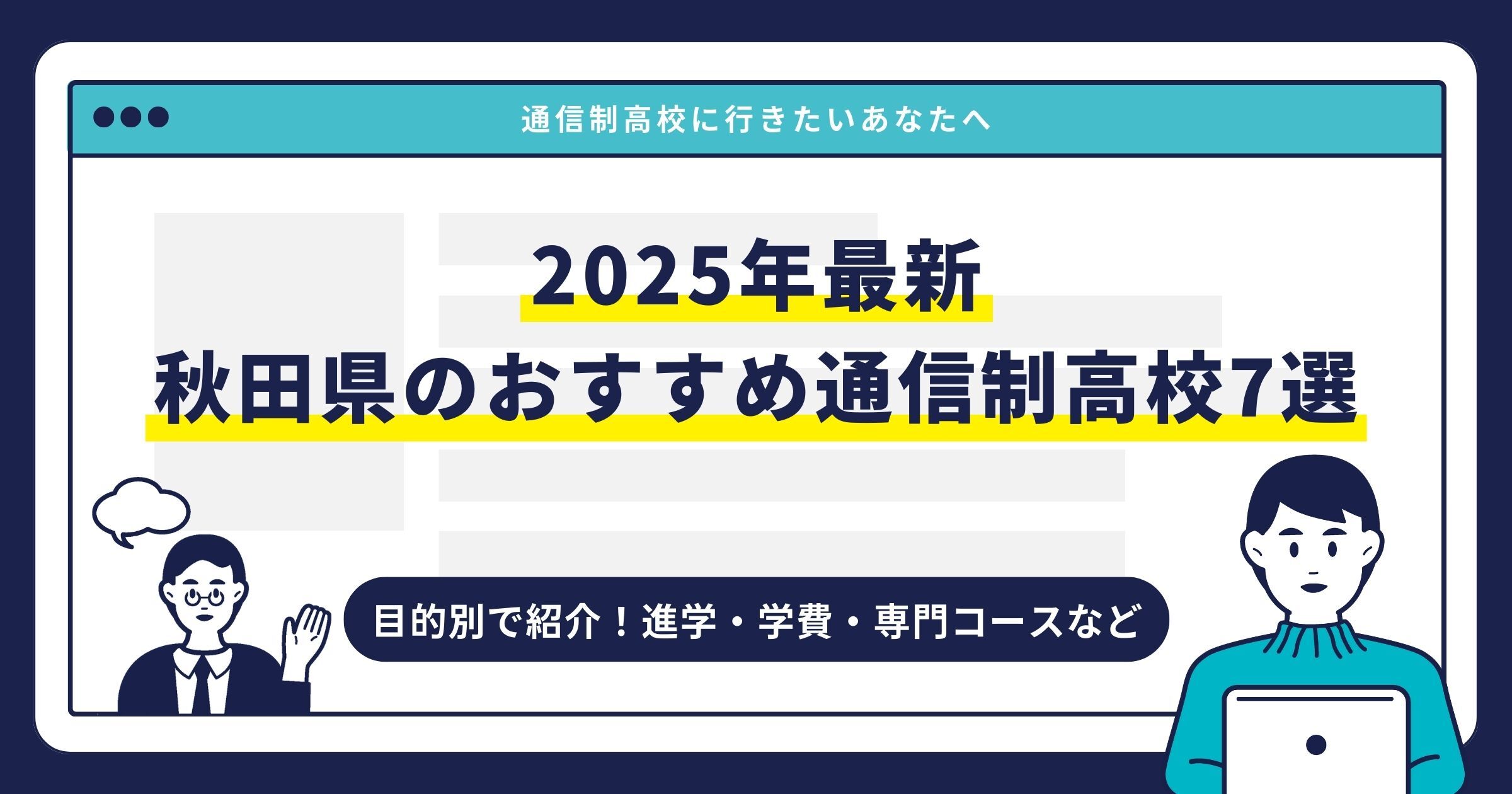
秋田県のおすすめ通信制高校【2025最新】目的別7校を紹介