記事を読むのにかかる時間 3分
進路やキャリアを考えるとき、どうしても合格や不合格など「目に見える結果」に目を向けがちですよね。けれど、「合格=幸せ」「不合格=不幸せ」とは限りません。受験や就活は人生のほんの一部にすぎず、その先にはまだまだ長い道のりが続いています。
重要なのは、結果の裏に隠れた見えないプロセスや、「どんな考え方で取り組んだのか」「何をしたいのか」という自分の思いです。ここにこそ、幸せを感じ充実した人生を送るヒントが隠れているのではないでしょうか。
今回は、人が幸せに生きるとはどういうことかを科学的に検証する「幸福学」の第一人者・前野隆司さんと、「第一志望合格」と「その先のキャリア」を見据えた学習塾「モチベーションアカデミア」を経営する佐々木快さんに、それぞれの専門分野から子どもの幸せな進路・キャリアについてお話いただきます。聞き手は、書籍『13歳からの進路相談』の著者・松下 雅征です。

【前野隆司(まえの たかし)さんは、こんな人】
|
1962年生まれ。武蔵野大学ウェルビーイング学部長、慶應義塾大学名誉教授。「人が幸せに生きるとは?」を科学的に検証する「幸福学」の第一人者。著書『「幸福学」が明らかにした 幸せな人生を送る子どもの育て方』(ディスカバー・トゥエンティワン)、監修『99%の小学生は気づいていない!?ウェルビーイングの魔法』(Z会)など多数。
|

【佐々木快(ささき かい)さんは、こんな人】
|
1995年生まれ。株式会社モチベーションアカデミア 代表取締役社長。早稲田大学を卒業後、2019年に同社に入社。渋谷校スクールマネジャー、企画室マネジャーを経て、現職。世界初の「モチベーション」にフォーカスした経営コンサルティング会社であるリンクアンドモチベーションのグループ会社において史上最年少で代表取締役社長に就任。
|
「幸せに働く」って、どういうこと?
松下 働くうえで、人はどのようなことに「幸せ」や「不幸せ」を感じるのでしょうか。
前野 まず、「幸せ」の定義についてお話ししましょう。私が大学で研究している「幸福学」では、心理学をもとに、アンケート調査から幸せを考えています。
たとえば、「あなたは今、どのくらい幸せですか?」と質問して、「とても幸せ」「かなり幸せ」「どちらでもない」「やや不幸せ」といった選択肢に答えてもらいます。
その回答を集めて、たくさんの人が「幸せ」だと感じている傾向と、そうでない人の傾向を統計的に分析するんです。つまり、幸せや不幸せの評価は、答えた人の感じ方に任せて、その集計から特徴を見つける方法をとっています。
では、働くなかでの幸せや不幸せってどう感じるのか? これを一言で説明するのは難しいのですが、「自己肯定感」や「自己受容」が高い人ほど、幸せだと感じやすいということがわかっています。
自己肯定感とは、自分のことを肯定的に受け止められること。「今、楽しいな」と感じたり、たとえ失敗しても「大丈夫。自分はよくがんばっているぞ」と思えたりする状態ですね。
似ている言葉に、自己受容があります。これも、自分の良い面も悪い面も両方を受けとめる力です。こうした自己肯定感や自己受容が高い人は、働く場面でも幸せを感じやすくなります。反対に、自己肯定感が低いと不幸せだと感じやすくなるんです。
松下 自分の状態を「良い」「悪い」と判断するのではなく、ありのままを認めることがポイントなんですね。では、どうすれば自己肯定感は高まるのでしょうか。
前野 いろいろな要因がありますが、なかでも「やりがい」と「つながり」が大切です。
「やりがい」とは、「この活動には意味がある」「自分はここで必要とされている」と思える感覚です。たとえば、学校の委員会の仕事でも「自分はこの役割を果たすことに意義を感じる」「この係は面白い!」と思えると、やりがいにつながり、幸せを感じやすくなります。これは「生きがい」や「働きがい」といった言葉でも表せます。
「つながり」も幸せに欠かせません。人と良い関係が築けたり、仲間と協力し合う場面が多かったりすると、幸せを感じやすいのです。孤立することなく、他者と尊重し合える環境が大切です。
部活動や文化祭の準備などでは、みんなで一つの目標に向かって頑張ることで自然とやる気が出て、ワクワクしますよね。「お金をもらう」といった報酬がなくても、楽しめます。
働く場面でも同じです。多様な人たちがお互いを信頼し、尊重し合いながら、共通の目標に向かって力を合わせる。「やりがい」と「つながり」があると、人は幸せを感じやすいのです。
時代や年齢を超えても「やりがい」と「つながり」の大切さは、大きく変わりません。社会がどんなふうに変化しても、人が幸せを感じるための土台として、これらは普遍的な要素だと考えられます。
自分から「幸せ」に近づいていこう
松下 では、働くことを幸せに感じる人には、どのような特徴がありますか。
前野 自分で考え、行動し、自分の人生に責任を持つ人は、幸せを感じやすい傾向があります。
さきほどお話ししたとおり、人に助けてもらえる環境や、まわりの人と支え合う「つながり」も大切です。さらに「やる気(やりがい)」を感じられる仕事や、自分を受け入れられる自己肯定感や自己受容の高さも関係します。
ようするに、主体性、つながり、やりがい、自己肯定感といった要素がそろうと、働くことに幸せを感じやすいんです。
また、仕事によって幸福度に違いがあるわけでもありません。どんな仕事でも、やりがいやつながり、自分らしさを生かせる環境を作れば、幸せに働くことは可能です。
松下 今のお話をうかがうと、「幸せ」か「不幸せ」かは、自分自身の捉え方に大きく左右されるように思えます。では、その感覚を自分でコントロールすることは可能なのでしょうか。
前野 幸せは「健康」にたとえるとわかりやすいです。健康になりたいと思って食生活や運動を見直す人は、少しずつ健康になりますよね。逆に健康をまったく気にせず、好きなものを好きなだけ食べたり、寝不足を続ければ、健康は損なわれていきます。
幸せも同じで、「幸せになりたい」と思い、幸せになるための行動や考え方を知れば、少しずつ近づけるでしょう。
松下 幸せになるための行動とは、先ほどお話しにあった、やりがいを感じられることに取り組んだり、自分のまわりのつながりを大切にすることですね。
前野 ただ「幸せにならなきゃ!」と強く思いすぎると、かえって不幸せを感じる場合もあります。
ポイントは、「やりがい」「つながり」「自己肯定感」を高めるような行動を、あまり気負わずに、「ちょっとやってみようかな」とポジティブに捉えることです。そうすると、自然と幸せに近づきます。
無理せず、自分を追いつめず、ちょっとずつ前向きに試していくことが大切です。時間がかかりますが、幸せの追求には、人生を通して取り組める面白さがあるのかもしれませんね。
「不合格=不幸せ」ではありません
松下 佐々木さんは、塾の先生として子どもたちと接しています。塾というと、受験に関わることが多いと思うんです。受験では、どうしても「合格=幸せ」「不合格=不幸せ」と考えがちですが、その後の人生が決まるわけではありません。合否以外に、大切なことがあるのではないでしょうか。
佐々木 受験の結果だけに注目してしまうと、その先の人生で幸せを感じにくくなる場合がありますね。
私は「目の前の結果がすべてではない」という考え方を大切にしているんです。たとえば、今回の受験は不合格でも、10年後に振り返ってみると、選んだ進路が自分にとって最良の選択だったと気づくことだってあります。
つまり、「その先」を見据えた考え方が大切で、受験というプロセス自体をどう過ごすかが、後から「受験をやって良かった」と思えるカギになるんです。
私たちの学習メソッド「モチアカ式」は、学習姿勢(学習エンゲージメント)と学習方法(学習スキル)の両面にアプローチしますが、やはり一丁目一番地は、前者の「いかに学びに主体的に向き合えるか」だと思います。
そういう本質を大切しているからこそ、結果として、非常に高い成果が残せているのだと確信しています。
主体性を持てれば、幸せを感じるチャンスも増えると考えています。受験に限らず、「やらされている」感覚ではなく、「自分の意思で取り組んでいる」という意識があると、自分の人生への納得感が高まるからです。
たとえば、自律的に考えて行動する、責任を自分で引き受ける、周囲からのサポートを上手に活用する、といった姿勢は、自分をより強く、前向きにしてくれます。
大人は子どもの環境にも目を向けて
松下 受験の合否に関わらず、幸せな進路を歩める子どもには、どんな特徴や傾向があると思いますか。
佐々木 私たちの塾では、「子どもを取り巻く環境をより良くしていく」というミッションを掲げています。なぜなら、幸せやウェルビーイングは、周囲の大人や仲間から「伝染」していくようなものだと考えているからです。
生徒たちが自分の人生に向き合う姿勢や考え方は、周囲の大人や友だち、つまりその子どもを取り巻く環境から大きな影響を受けるんです。私たちは、自分たちがまず本気のパートナーとして生徒に向き合います。そして、ご家族や学校とのつながりに対しても、「子どもの環境をより良くしていきたい」という考えを共有していこうとしています。
たとえば、受験が厳しい道のりになりそうなら、家族や友人との関わりを安心できる居場所にしてあげる。もし受験がそこまで厳しくないなら、ほかのチャレンジに挑戦できる環境を選ぶといったように、環境のバランスを整えることが大切だと思います。
こうした「環境」が生徒をしっかりサポートできていると、どんな結果でも、その先を見据えて幸せに生きていく生徒が多いと実感しています。
運よく、環境が良い、または環境づくりがうまくいっている生徒は、受験の結果にかかわらず「この先もうまくやっていけるんじゃないか」と感じさせるものがあります。大人としては、環境と本人を一体として考えることが重要だと感じています。
松下 お話を聞いて、私自身も共感します。私が経営する通信制の学校でも、「生徒に安心できる居場所を用意する」ことを大切にしています。忙しい全日制の進学校から転校してきた生徒が、スケジュールに余裕ができたとたん、「バイトに挑戦してみよう」とか、「新しいことに興味が湧いてきた」というように、自分から動き出すことが多いんです。
こちらから「これをしなさい」と指示しなくても、環境が変わるだけで生徒の主体性や考え方が大きく変わるのを目の当たりにしました。ですから、佐々木さんが「生徒を取り巻く環境を総合的に整えることが大切」というお話は、私自身の経験からも「そうだよな」と強く感じます。
子どもの進路や未来はひとつじゃない
松下 では、自分にとって幸せな進路や働き方を見つけるための、具体的なアクションを教えてください。
前野 2つあります。1つ目は、人と比べないことです。「あの子はスポーツができる」「自分より偏差値の高い学校へ行っている」のように他人と比較して落ち込むのではなく、自分らしさを見つけてほしいなと思います。
2つ目は、広い視野を持つこと。これから、まるで明治維新直後や戦後復興期のような劇的な変化が起こるかもしれません。そんな時代には、既存の枠組みにとらわれないで、自分の個性や強みを生かしていく力が求められます。
つまり、勉強だけに没頭せず、部活動や趣味、人との交流など、いろいろな世界に飛び込み、多様な経験を積んでほしいのです。小さな子どもやお年寄り、外国の人たちなど、年齢や国境を越えて交流する。新しいテクノロジーに触れたり、世界の課題に目を向けたりすることも大切です。「やりがい」「つながり」を感じ、「自己肯定感」を高めるための、さまざまな挑戦を恐れず楽しんでほしいですね。
日本の将来を暗く考える人もいますが、技術の進歩や国際交流の拡大を考えると、未来には大きな可能性が広がっています。日本の子どもたちは、学力も高いし、創造性もある。皆さんには、今よりもっと豊かでおもしろい未来が待っていると、私は本気で思っています。ぜひ、「未来は明るい」と信じて、ワクワクしながら新しいことに取り組んでほしいです。
松下 佐々木さんからは、高校受験や大学受験を控える子どもたちに、「自分が納得できる進路の見つけ方」のアドバイスを聞きたいです。
佐々木 受験は、自分の人生をより良くするための「たくさんある選択肢の一つ」に過ぎません。受験で選ぶ進路だけが、人生のすべてではないんです。
受験では「合格すること」が目的になりがちですが、そうではなくて、「自分はどんな生き方をしたいか」「どんな価値観を大事にしたいか」という、もっと根本的な軸や目標と、受験を組み合わせて考えてみてはどうでしょうか。
たとえば、「まわりの人に笑顔を届けられる人になりたい」とか「将来、こんなことを実現したい」という自分なりの想いを見つけてみる。それと受験を結びつけることで、「なぜ勉強するのか」「なぜ挑戦するのか」が自分の中でスッと理解できるようになります。
松下 「受験はやるものだ」「合格しなきゃ」と考えるのではなく、「受験はあなたの人生を豊かにするための手段の一つだよ」ということですよね。そして受験に挑戦するならば、自分なりの意味や目的をしっかり見つけてから取り組むのが大切ですね。
自分や世界をポジティブなメガネで見つめよう
松下 最後に、読者の皆さんへメッセージをお願いします。
 前野
前野
|
あらためて、視野を広く持つことはとても大切だと強調したいです。「視野が広い人は幸せになりやすく、逆に視野が狭い人は不幸せになりやすい」という研究結果もあります。
視野が狭くなる例としてわかりやすいのが、「受験のために部活や趣味をやめる」ということ。できれば勉強とほかの活動をうまく両立してほしいですね。合格そのものが人生のゴールではありません。受験は「成功しても失敗しても、人生の糧になるチャレンジ」なのです。 実は「苦しい経験」を乗り越えた人のほうが、のちのち高い幸福度を感じやすいという研究結果もあります。嫌なことをさけるよりも、チャレンジをくり返していくほうが、幸せに近づくんです。 コスパやタイパって、一見「効率的」に見えるかもしれません。でも、最短距離だと思っていたら、実は大きな幸せから遠ざかっていたり、遠回りになってしまう可能性がある。 だから、受験で思っていたような結果にならなくても、がんばったことは財産になると考えてください。努力はムダになりません。これからの人生で、受験以外にも何度もチャンスがあります。ぜひ「未来は明るい」という視点を忘れずに、思いきって行動してほしいです。 |
 佐々木
佐々木
|
視野を広く持つこと、自分や世界をもっと知ろうとすること。これは、一見コスパが悪いように見えるかもしれませんが、実はそうした「寄り道」や「試行錯誤」が、将来あなたの人生をとても豊かにしてくれます。
「自分はどんな存在なのか」「世の中にはどんな可能性があるのか」といった問いに向き合い、自分なりの答えを探していく。その過程で、たとえば家の手伝いをしたり、小さな挑戦をしたりして、「世界をつくっていく一員」になる感覚をつかんでほしいんです。そうした経験が将来の進路選びや受験、キャリアの形成に大いに役立ちます。 私たちは、世の中や自分自身を「メガネ」を通して見ています。このメガネを、意識的に変えてみましょう。皆さんは、あなた自身が思っている以上に、可能性や価値にあふれた存在です。世界も、正しい姿勢で向き合えば、とても魅力的な場所であることに気づくはずです。 「自分はダメかも」「社会は暗いかも」といったメガネではなく、「自分にもきっとできる」「世界にはたくさんのチャンスがある」というポジティブなメガネをかけてみる。きっと新しい景色が見えてきますよ。 |
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
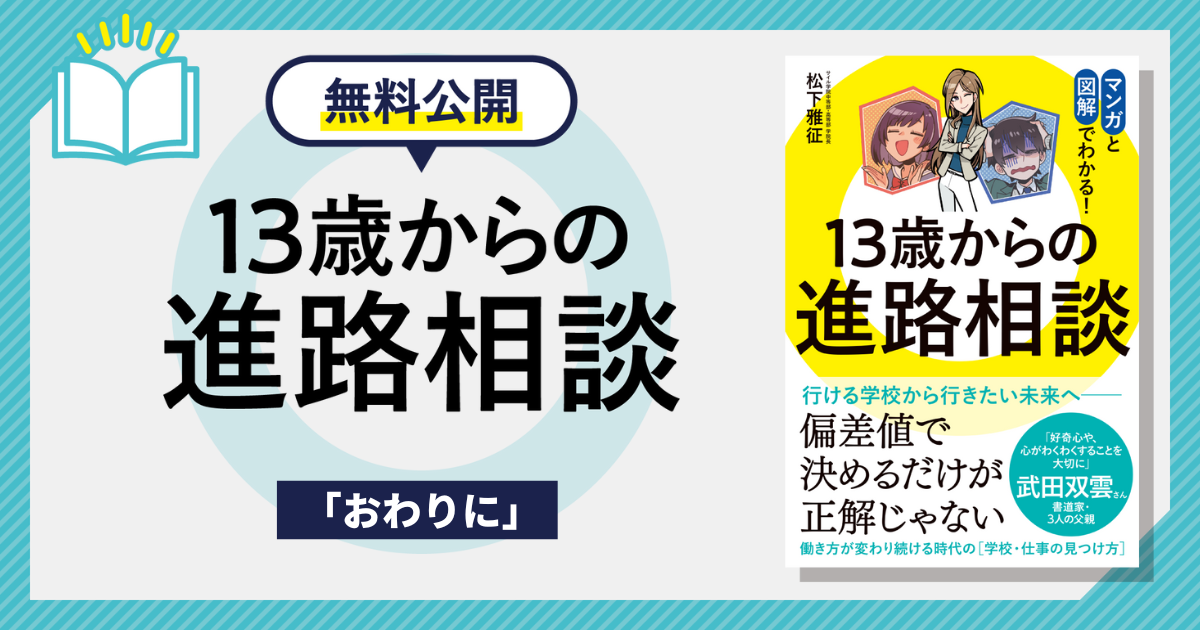
【無料公開】書籍「13歳からの進路相談」おわりに
次の記事
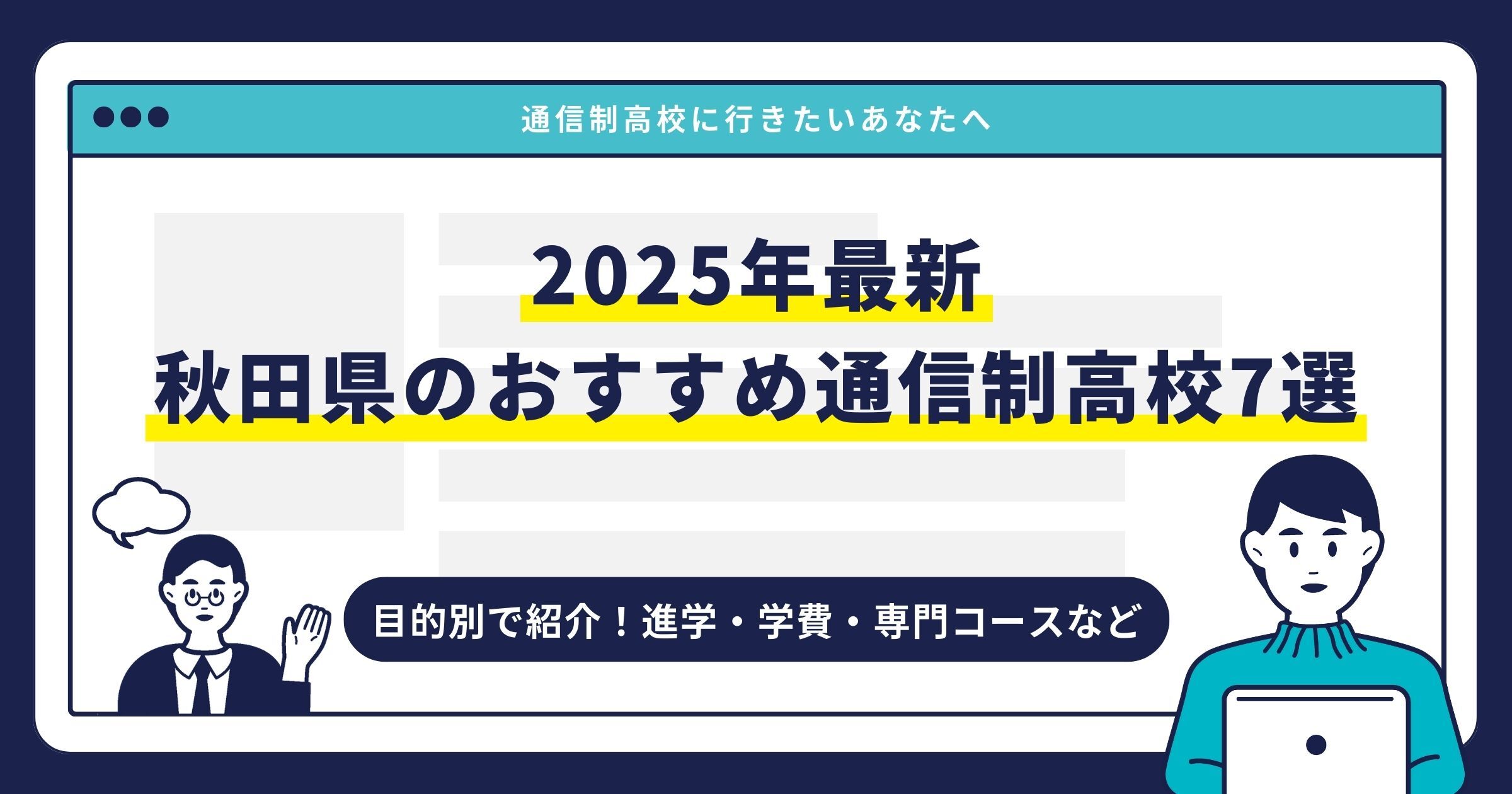
秋田県のおすすめ通信制高校【2025最新】目的別7校を紹介

.png)