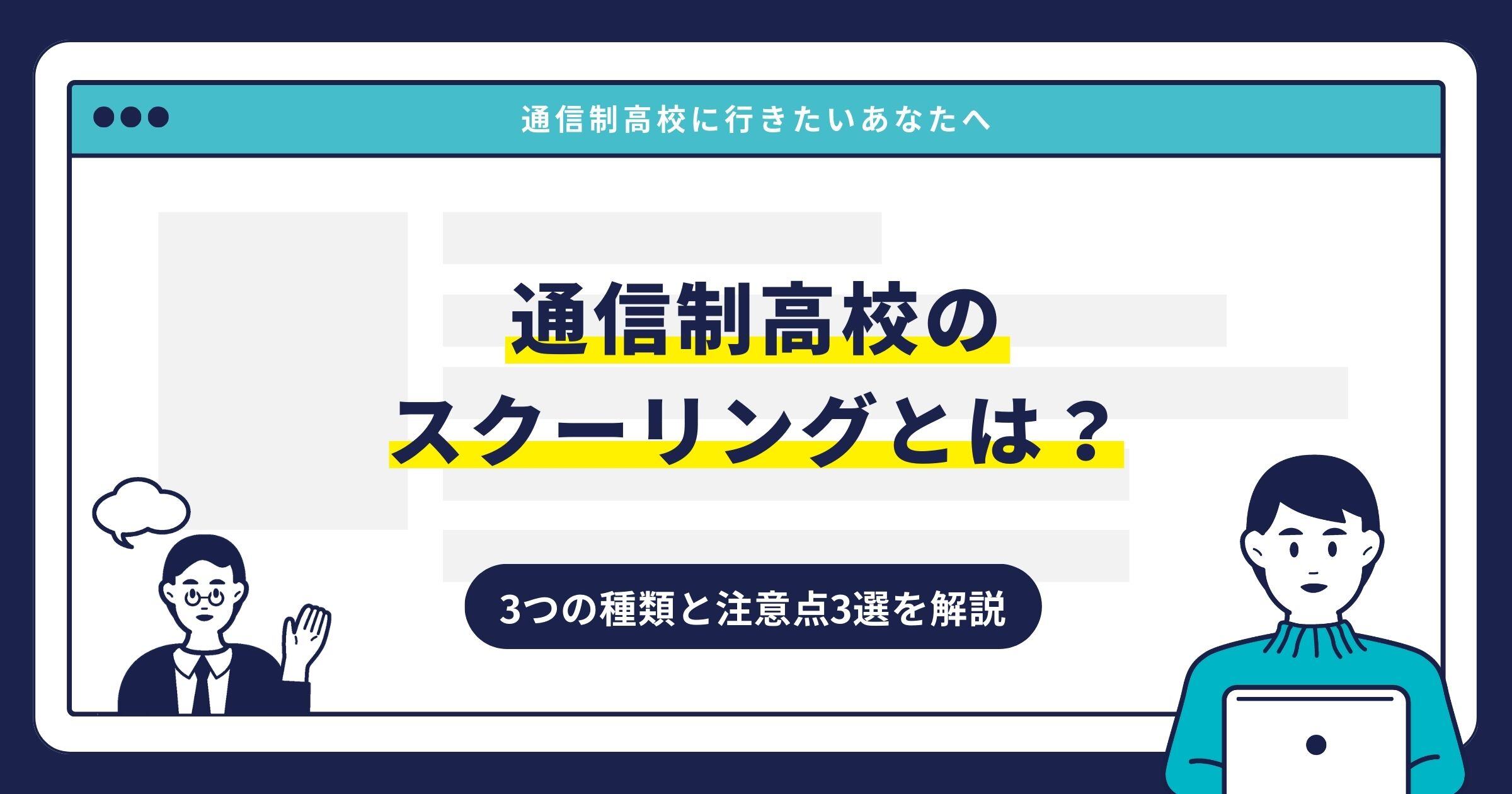記事を読むのにかかる時間 3分
「登校しなくてよい」と思われがちな通信制高校ですが、スクーリングと呼ばれる定期的な通学が必要です。
通信制高校のスクーリングは、教科の単位取得や卒業に欠かせない要件。
スクーリングには様々な種類があるため、自分に合った通学方法を選ぶことが重要です。
スクーリングを上手に活用すれば、充実した高校生活を送れます。
 進路相談のプロ
進路相談のプロ
|
本記事では、通信制高校のスクーリングについて知りたい高校生の方へ、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が、スクーリングの基本から3つの種類、選び方のポイントまで丁寧に解説します。 |
【通信制高校に入学・転入したい方へ】
通信制高校のスクーリングとは
まずは、通信制高校のスクーリングに関する基本知識を解説します。
通学・対面授業の必修科目
通信制高校では、スクーリングと呼ばれる対面授業を行います。
スクーリングでは、教科書やプリントを使用した講義に加え、体育実技や理科の実験、家庭科の調理実習など、自宅では行えない実践的な学習活動を行います。
なお、高校のカリキュラムでは「1単位時間」を50分として定めています。
以下の通り、スクーリングに必要な時間は、文部科学省が定める高等学校学習指導要領に基づき、すべての通信制高校で実施されています。
| 各教科・科目等 | スクーリング必要時間(単位時間) |
| 国語、地理歴史、公民及び数学 | 1 |
| 理科 | 4 |
| 体育 | 5 |
| 保健 | 1 |
| 芸術・外国語 | 4 |
| 家庭・情報、専門教科・科目 | 各教科・科目の必要に応じて2~8 |
参考:各教科・科目の面接指導の単位時間の標準(「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者会議 資料2
スクーリングは、知識習得だけでなく、不明点を質問したり、レポート作成の助言を受けたりする機会にもなります。
教科書や教材だけでは理解しにくい内容も、授業や他の生徒と一緒に学習することによって深く理解できます。
単位修得に必要
通信制高校で単位を修得するためには、レポート提出やテストに加えて、科目ごとに定められた回数のスクーリングが必須です。
スクーリングでは、授業への出席、課題提出、試験、グループワーク、発表などを通して評価が行われます。その評価に基づいて単位が認定される仕組みです。
科目によっては、スクーリングへの参加が単位修得の必須条件となっています。
例えば、体育や芸術科目など、実技を伴う科目は、スクーリングで実技指導を受ける必要があるケースが多いです。
また、実験を伴う理科科目や、ディスカッションやプレゼンテーションを行う科目なども、スクーリングで実践的な学習を行う場合があります。
科目を履修する際に、スクーリングの必要時間や参加方法などを確認しておくと良いでしょう。
特別活動への参加
通信制高校の卒業要件には、教科の単位取得に加えて「特別活動」への参加が定められています。
卒業までに最低30単位時間以上の特別活動への参加が必要です。
特別活動は、ただ卒業のための要件を満たすためだけのものではありません。他の生徒や先生と交流し、学校生活を充実させるための重要な機会です。
以下の活動は、スクーリングの一環として実施されます。
✓特別活動の例
- ホームルーム(学級活動や学年集会)
- 進路指導、ガイダンス、個別相談
- 学校行事(文化祭、体育祭、修学旅行など)
- 生徒会活動・委員会活動
- クラブ活動
- ボランティア活動
スクーリング時に特別活動に参加することで、普段はなかなか会えない生徒同士の交流を深め、友達を見つける貴重な機会にもなります。
欠席するとどうなるか
スクーリングへの出席は、多くの科目で単位修得の要件となっています。
必要な単位数が不足すると、卒業が遅れる可能性もあります。学校によっては、スクーリングの出席日数が進級の要件に含まれています。
ただし、通信制高校では、正当な理由がある場合の欠席に対して柔軟な対応を取ることが多いです。
学校によっては、以下のような対応を取ってくれる場合があります。
✓スクーリングを欠席する際の代替策の例
- 別日程での振り替え受講
- レポート提出
- オンライン授業への参加
欠席が避けられない場合は、必ず事前に学校へ連絡し、対応方法を相談することが重要です。入学前に学校のサポート体制を確認しておくと良いでしょう。
スクーリングの3つの種類とメリット・デメリット
通信制高校のスクーリングには、大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの形式によって、メリット・デメリットが異なるので、自分に合ったスクーリングの種類を選びましょう。
通学型スクーリング
通学型スクーリングは、全日制高校のように、週に数回、決まった曜日に学校へ通学して授業を受ける形式です。
✓通学型のメリット
- 生活リズムが整いやすい
- 学習習慣が身につく
- 友達と交流する機会が増える
- 先生への学習相談や生活相談が可能
- 全日制のような学校生活を満喫できる
✓通学型のデメリット
- 通学に時間と費用がかかる
- 自宅から通える学校を選ぶ必要がある
- アルバイトや習い事など他の予定との調整が難しい
通学型スクーリングは、全日制高校に近い形で学校生活を送りたい人や、先生や友達との交流を重視する人に向いています。
学校によって通学頻度は異なり、全日制高校のように週5日通うコースから、週1回や月2回程度のコースまで、様々なスタイルが用意されています。
| 学校名 | スクーリング頻度 | 特徴 |
| クラーク記念国際高校(通学コース) | 週5日 |
学年別の習熟度別授業 プログラミング、eスポーツなどの専門コース グループごとに行うプロジェクト型学習 |
| 飛鳥未来高校 |
ベーシック(月1回) スタンダード(週1回) 3DAY(週3回) 5DAY(週5回) |
進学や美容師免許など専門コースを受講できる 文化祭など参加自由の学校行事がある 担任やスクールカウンセラーからの心理支援 |
| N高校・S高校(通学コース) |
週1(木) 週3(月・水・金) 週5(月・火・水・木・金) |
プロジェクト学習やプログラミングなどの学習過程 サークルやコミュニティ活動への参加が可能 ティーチングアシスタントによる学習支援 |
集中型スクーリング
集中型スクーリングは、長期休暇(ゴールデンウィーク、夏休み、冬休みなど)や週末などを利用して数日間まとめて授業を受ける形態です。
1日の授業時間を長めに設定し、短期間で必要な学習時間を確保します。
✓集中型のメリット
- 短期間で多くの授業を受けられる
- 遠方の学校に通いやすい
- 自分のペースで学習を進めやすい
✓集中型のデメリット
- 集中的に学習するため体力が必要
- 交通費や宿泊費など費用が高くなる場合がある
- 通学型に比べて、先生や友達と交流する機会が少ない
集中型スクーリングは、効率的に学習を進めたい人や、遠方の学校に通いたい人に向いています。
決まった曜日に通学する必要がないため、仕事や芸能活動、スポーツなど、他の活動と両立したい人にも適しています。
| 学校名 | スクーリング頻度 | 特徴 |
| 勇姿国際高校 |
千葉、福岡、熊本、宮崎の学習センターに通学 年5~7日 |
宿泊不要で家から通える 春・夏・秋・冬から好きな時期を選べる 進路相談や面接練習も可能 |
| ルネサンス大阪高校 |
大阪・梅田の校舎に通学 年7~9日 |
日帰り登校が可能 土日のみの日程などの分散登校も可能 |
| ID学園高校 |
東京・文京区の校舎に通学 年5~7日 |
宿泊を伴わない通い型 関東エリア在住の生徒限定 前期7~8月、後期12月に開催 |
合宿型スクーリング
合宿型スクーリングは、年に1~2回程度、宿泊施設に滞在しながら3~4日間程度の集中的な授業を受ける形態です。
沖縄や北海道などのリゾート地で実施されることも多く、その土地の文化や自然に触れる体験学習なども組み込まれています。
スクーリングの回数を最小限に抑えられることから、遠方に住む生徒や、普段の通学が難しい生徒に人気があります。
✓合宿型のメリット
- 普段会う機会が無い人と友達になれる
- 普段とは違う環境で学習に集中できる
- レクリエーションや文化体験などが豊富
✓合宿型のデメリット
- 宿泊費や食費、活動費など、費用が高くなる
- 数日間家を空ける必要がある
- 集団生活に馴染めない場合がある
合宿型スクーリングは、修学旅行のような気分も味わえ、高校生活の思い出作りにもなります。
学習以外の体験活動も充実したスクーリングを提供する学校も多いです。
| 学校名 | スクーリング頻度 | 特徴 |
| サイル学院 高等部 | 沖縄で年1回(6泊7日) |
毎月開催しており好きな時期を選べる 生徒同士のマッチングもサポート可能 宿泊・食費などの費用が安い |
| 一ツ葉高校 |
近隣の方:前期・後期の年2回(2泊3日) 遠方の方:年1回(3泊4日) |
熊本県山都町での宿泊 日本の伝統芸能に触れる体験学習 カヌーや農業などの体験学習 |
| 屋久島おおぞら高校 | 屋久島で年1回(4泊5日) |
屋久島での自然体験 協調性を育むグループワーク |
サイル学院高等部は沖縄県のリゾートエリアでの年1回の合宿型スクーリングを実施しています。
詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
スクーリングの注意点3選
通信制高校で学習する方にとってスクーリングは重要な機会になります。
3つの注意点を意識することで、充実したスクーリング学習が可能になるでしょう。
オンライン学習と組み合わせる
スクーリングに加えて、インターネットを利用したオンライン学習を取り入れている通信制高校も少なくありません。
文部科学省の基準により、ラジオ、テレビ、インターネットなどのメディアを活用した学習を行うことで、スクーリング時間の最大60%まで免除が可能です。(*)
通学の負担を軽減できるだけでなく、自分のペースで学習を進められます。
ただし、オンライン学習は、自分のペースで進められる分、計画的に学習を進めることが重要です。目標やスケジュールを立てて、計画的に学習を進めましょう。
サイル学院 高等部のようなオンライン個別指導を提供する学校もあります。
✓オンライン学習サポート
- 担任の先生と週30分のテレビ通話
- 個別のチャットスペースで先生に相談できる
- 「受験」「起業・ビジネス」「海外進学」などの進路サポートが可能
ただし、オンライン学習の制度は学校によって異なります。
どの程度までスクーリング免除が可能か、どのような手続きが必要かなど、入学前に確認しましょう。
また、対面学習も大切な学びの機会なので、オンラインと対面授業のバランスを考慮することが重要です。
* 出典:高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン (令和5年2月一部改訂)
日程・年間スケジュールを確認する
通信制高校のスクーリングは、学校やコース、科目によって、日程や内容が大きく異なります。
集中型や合宿型の場合、定員に達してしまうこともあります。参加を希望する場合は、早めに予約しましょう。
スクーリングの日程は学校側が設定するため、自分の都合に合わせて変更することは基本的にできません。
年間スケジュールを早めに確認し、仕事や私生活との調整を行ってください。
入学前に年間の実施時期や回数を確認し、自分の生活リズムに合わせて無理なく参加できるかどうかを検討しましょう。
無理なく通える会場を選ぶ
通信制高校のスクーリング会場は、学校によって異なります。
通学時間が長すぎると体力的な負担が大きくなり、学習意欲の低下にもつながりかねません。
複数の会場から選択できる学校もあるので、自分の状況に最も適した会場を選びましょう。
✓スクーリング会場選びのポイント
- 通学時間
- 交通手段
- 交通費(定期や割引の有無)
- 周辺環境
- 交通アクセス
スクーリング会場の情報は、学校のホームページに掲載されていることが多いです。会場までのアクセス方法や周辺環境なども確認できます。
学校説明会に参加して、スクーリング会場について質問しましょう。実際に会場を見学できる場合もあります。
自分に合った通信制のスクーリングを利用しよう
通信制高校のスクーリングは、単位・卒業資格を得るためだけでなく、学習内容の理解を深めたり、先生や友達と交流したりする機会になります。
学校によって週5日通う通学型から年数回の合宿型まで形態は多様。通いやすいスクーリングを選べば、充実した高校生活を送れるでしょう。
自分のペースで通学できる通信制高校を探しているなら「サイル学院 高等部」の公式サイトを見てみてください。
年1回の合宿型スクーリングで、ほぼ毎月スクーリングを実施しているので、好きな時期を選べます。
通信制高校を探すなら【サイル学院の資料請求】がおすすめです。
サイル学院は、学校のふつうをなくした『ちょうどいい』学校。完全1対1の個別サポートで高校卒業とその先の進路まで伴走します。全国から毎月いつでも転校生を受け入れています。
▼生徒への質問
▼毎週実施する1on1【切り抜き】
資料請求いただいた方には、サイル学院の学校案内資料に加えて、通信制高校や進路の選び方がわかる資料もプレゼント中です。
「通信制高校のルールがわからない…」
「種類が多すぎてどれを選べばいいか迷う…」
「サイル学院と他校との違いを知りたい」
などの疑問や不安は、サイル学院の資料請求で解決できます。
資料は未成年の方・生徒ご本人も請求いただけます。お気軽に請求ください。
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
.png)
コスパ・タイパよりも、寄り道をしていこう【幸福学の第一人者・前野 隆司教授✕学習塾モチベーションアカデミア代表・佐々木 快さん】
次の記事
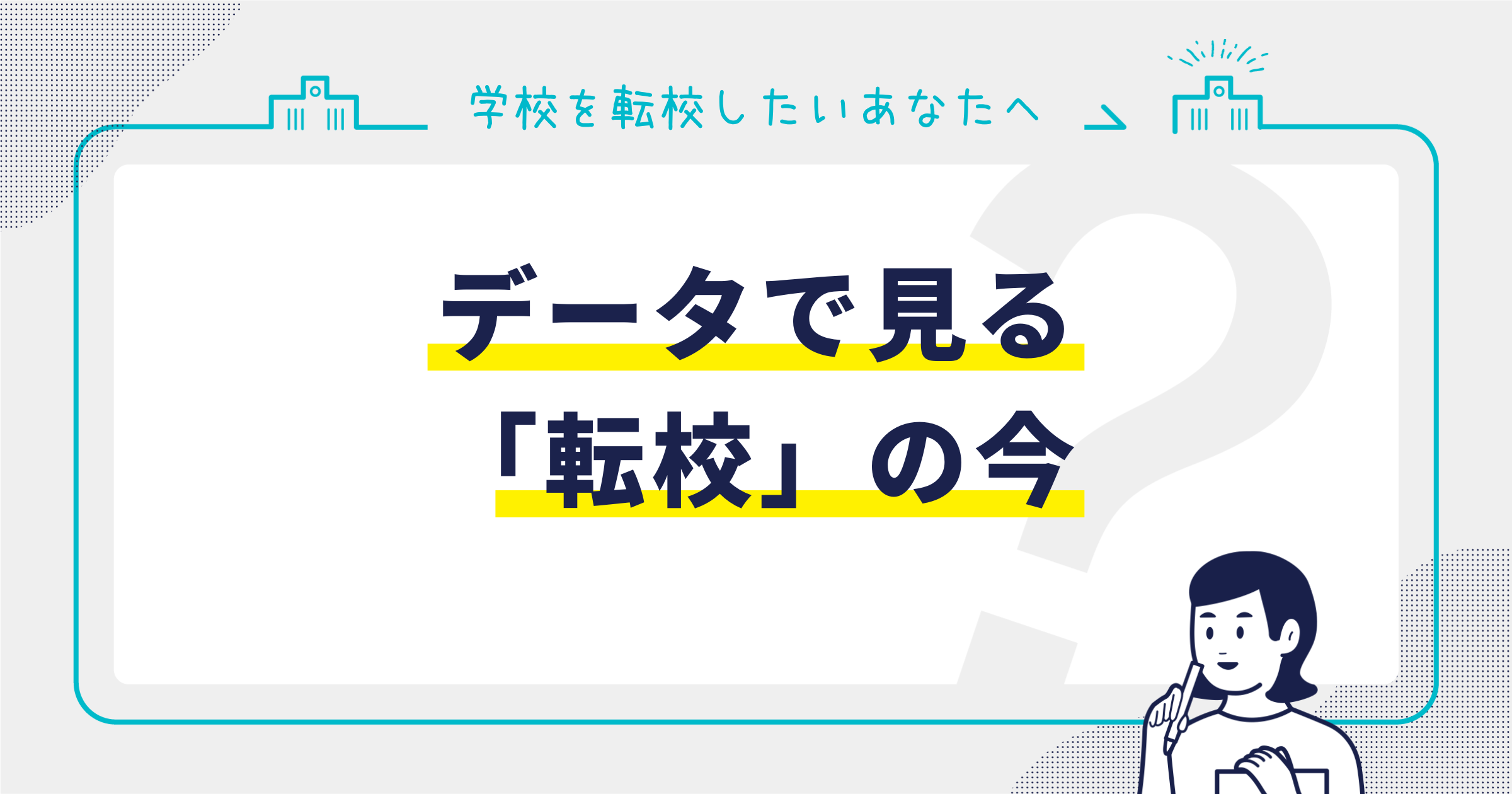
データで見る「転校」の今