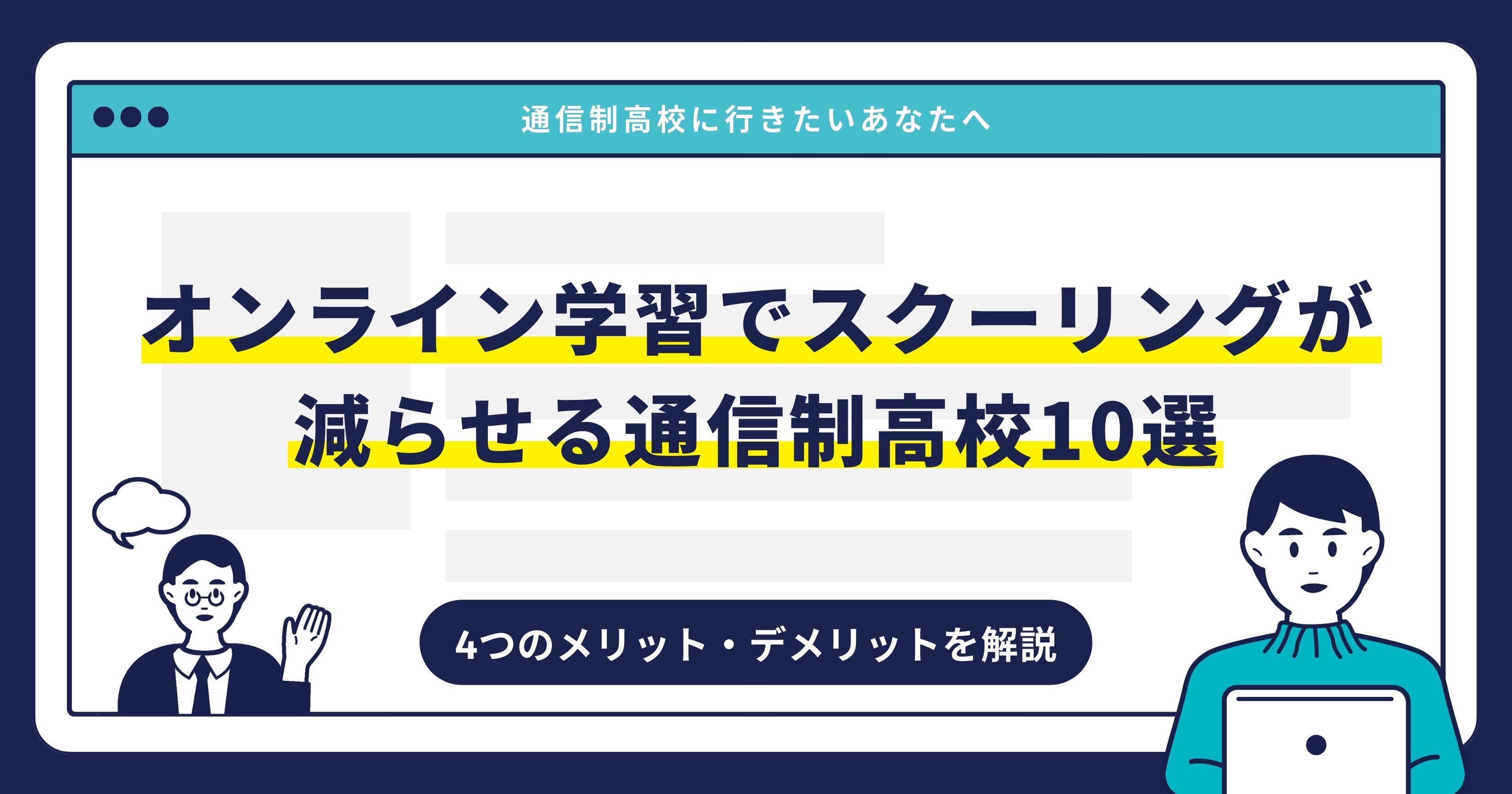記事を読むのにかかる時間 3分
「通信制高校のスクーリング代わりにオンラインでの学習は可能?」
このように考えていませんか。
結論、高校卒業に必要な単位を修得するためにスクーリングは必須です。
しかし、オンライン(メディア)学習で最大60%までスクーリングを減免できます。(*)
* 参考:各教科・科目の面接指導の単位時間の標準(「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者会議 資料2)
 進路相談のプロ
進路相談のプロ
|
本記事では、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が、スクーリングが少なくオンライン学習がメインの通信制高校やサポート校10選を紹介。オンライン学習を充実させてスクーリングを減らすメリット・デメリットも解説します。 |
【通信制高校に入学・転入したい方へ】
目次[非表示]
オンライン学習でスクーリングが減らせる通信制高校・サポート校10選
オンライン学習が充実している通信制高校・サポート校は、年間5~7日の短期集中スクーリングを提供していることが多いです。
ここでは、10校を紹介します。
| 名称 | スクーリングの特徴 | オンライン学習の特徴 |
| サイル学院 高等部 | 年1回・6泊7日(沖縄県) | 担任の先生と週30分のテレビ通話 個別チャットスペースでいつでも相談できる 大学受験・起業・海外進学など進路に合わせた個別指導 |
| N高校 | 1年次・3年次は全国拠点で7~8日のスクーリング 2年次は全国拠点で4~5日、沖縄県の本校スクーリング4~5日が必須 |
パソコン・スマホ・タブレットで使用できる映像と教材が一体化した「ZEN Study」 ネット部活や同好会が充実 |
| ルネサンス高校 | 3泊4日の本校スクーリング(茨城県) 生徒の事情に応じて分割型や日帰り型、親子参加型などを選べる |
ネットで完結するレポート学習・提出環境 予備校など専門講師による授業動画「スタディサプリ」も利用可能 |
| ワオ高校 | 年2回・3泊4日の宿泊型スクーリング(岡山県) | Zoomを利用した議論型オンライン授業 バーチャルキャンパス(掲示板・チャット)で同級生や先生とつながる |
| 一ツ葉高校(ゼロ・ライトコース) | 近郊:年2回・2泊3日 遠方:年1回・3泊4日 (熊本県) |
スマホ・タブレットでの動画視聴やレポート学習 学校行事や部活動もネットで開催 |
| 勇志国際高校(メタバース生) | 年1回・4泊5日のスクーリング(熊本県の本校の他、熊本、福岡、千葉、宮崎に学習センターあり) | VR機器を無償貸与 アバターを利用してホームルームや授業に参加できる オンラインのeスポーツ大会や学校祭などイベント充実 |
| アットマーク国際高校 | 年1回・3~4日(石川県) | 担任制度・1対1の個別コーチング 自ら学習テーマを決めて取り組む「マイプロ」で単位認定 |
| 第一学院高校(Mobile HighSchool) | 年1回・3~4日(茨城県・兵庫県など) | 担任制度・オンライン学習室で仲間と一緒に学べる オンライン三者面談で進路指導充実 |
| ID学園高校 | 日帰り型・年6日程度の東京集中スクーリング(他に長野での宿泊型スクーリングあり) | 授業はZoom生配信・YouTubeで見直しも可能 担任制でオンラインホームルームや進路指導あり |
| おおぞら高校 | 年1回・屋久島スクーリング | 教員によるオンライン(電話)サポート オンライン実習や体験授業に参加できる |
【通信制高校に入学・転入したい方へ】
スクーリングの代わりにオンラインで学習するメリット4選
スクーリングをゼロにすることはできませんが、オンライン学習を併用することで自由度が高まります。
ここでは、通信制でオンライン学習を活用するメリットを解説します。
1. 通学の負担が少ない
オンライン学習の最大のメリットは、時間や場所に縛られずに学習できることです。
スクーリングが少ないので、通学の負担を軽減できます。
従来の通信制高校では、スクーリングのために年間20日程度の通学が必要でした。
しかし、近年ではオンライン学習(メディア学習)の活用により年間5~7日程度まで通学日数を削減する学校も増えてきました。
授業がオンライン学習メインになることで、心身のストレスが減ったという生徒の声もあります。
「起立性調節障害が原因で高校1年生の6月頃から学校に通えなくなったんです。...朝早くに登校して、詰め込み学習をして、部活で疲れて帰るという生活も、僕には合いませんでした。...しかし、サイルに転入した今、それらの不満はなくなりました。朝はパソコンを開けばすぐに登校できます。」(静岡県在住・サイル学院高等部の生徒)
オンライン学習でスクーリングを減らすことで、通学にかかる費用を大幅に削減できるのもメリットです。
✓通学にかかる費用の例
- 通学定期代・交通費
- 遠方でのスクーリング宿泊費
- 制服(指定されていれば)
サイル学院の場合、通学は年1回のみ。6泊7日の沖縄スクーリングの費用も宿泊費や食費などの諸経費込みで1万円台との生徒の声があります。
参考:サイル学院高等部 短期集中スクーリング
スクーリングの経済的負担が軽くなることで、地方在住の生徒にとって進学の選択肢が広がります。
2. 人間関係のストレスが少ない
人間関係のストレスが軽減されるのもオンライン学習を取り入れた通信制のメリットです。
全日制高校では、クラスメイトや部活動の仲間など、様々な人と関わる機会が多く、中には苦手な人や合わない人と無理に接しなければならない状況も生まれます。
一方で、オンライン学習がメインの通信制では、集団行動のプレッシャーが少ないです。
「授業の先生は優しいし、担任の先生は親身に相談にのってくれる。一方で、オンラインだからずっと一緒にいるわけじゃない。ちょうどいい距離感。人間関係で感じていたストレスからも解放されたので、気持ちが楽になりました。」(静岡県在住・サイル学院高等部の生徒)
オンライン学習がメインの通信制でもコミュニケーションがゼロになるわけではありません。
例えば、サイル学院では、個別のチャットスペースで先生に質問が可能。担任と週30分のテレビ通話などのサポート体制が充実しています。
画面越しのコミュニケーションは、対面よりも心理的なハードルが下がるため、積極的に参加できる生徒もいます。
3. 自分のペースで学習できる
オンライン学習の特徴は、一人ひとりの理解度や生活リズムに合わせて自分のペースで学習を進められることです。
オンデマンド形式(いつでも好きな時間に学習できる教材)の授業では、動画を一時停止したり巻き戻したりしながら、自分のペースで学習内容を理解していくことができます。
難しい箇所は時間をかけて理解し、理解しやすい箇所はテンポよく進めることができます。
「全日制の学校に通っていたときは、朝は早いし、授業が終わるのは16時半くらい。そのあと部活をやってから帰るので、復習や予習をしていたら、自分のやりたい勉強はなかなかできなかったんです。いまは、自分の好きな勉強を、好きなだけできるので楽しいですね。」(新潟県在住・サイル学院高等部の生徒)
朝型や夜型など生活リズムに合わせて学習時間を設定できることもメリット。
スポーツや芸能活動に励む生徒、体調に波がある生徒など、様々な事情を持つ生徒たちも、自分のコンディションが最も良い時間帯に学習を行えます。
多くの通信制で導入されている学習管理システムにより、教材やレポートの提出状況などを確認しながら計画的に学習を進めることが可能です。
4. 多様な学習コンテンツ
従来の教科書などの印刷教材だけでなく、多様なコンテンツを使ったオンライン学習に対応した通信制も多いです。
✓多様な学習コンテンツの例
- 動画:講師の授業録画や図解を用いた解説動画
- ライブ:双方向の授業を生配信で受信
- 交流:アバターを利用したバーチャル空間での交流
リアルタイムのライブ授業では、チャット機能を使って気軽に質問できたり、画面共有機能で教材を見ながら詳しい説明を受けたりできます。
また、「すらら」や「スタディサプリ」といった学習支援プログラムと連携している学校も多いです。
それぞれの生徒の理解度に応じた最適な教材で効率的に学習を進められます。
サイル学院のように、将来の進路やキャリアにつながる学習プログラムを受講できる通信制も少なくありません。
「ビジネスや起業に興味があったようですし、少しでも将来に直接役立つスキルであったりを、ネット環境さえ整えれば家に居ながら身につけられるサイルを一緒に探して選びました。」(三重県在住・サイル学院高等部 生徒のお母様)
多様なコンテンツを組み合わせることで、スクーリングを減らしても学習の効果性が損なわれない工夫が施されています。
【通信制高校に入学・転入したい方へ】
スクーリングの代わりにオンラインで学習するデメリット4選
オンライン学習中心の通信制高校では、スクーリングで先生に質問したり、生徒同士の交流を楽しんだりする機会が少なくなりがちです。
ここでは、通信制でオンライン学習を活用するデメリットを解説します。
1. オンライン学習環境が必須
通信制でオンライン学習を始めるにあたって、まず必要になるのは学習環境の整備です。
✓オンライン学習環境の例
- 安定したインターネット回線
- パソコンやタブレットなどのデバイス
- Webカメラやマイクなどの周辺機器
オンライン学習では、動画視聴や教材ダウンロードなど大量のデータ通信が発生するため、光回線など安定した高速インターネット回線が必要です。
モバイルWi-Fiルーターやスマートフォンのテザリング機能を利用する場合、データ通信量の上限に注意が必要です。
オンライン学習環境を整えるには、一定の費用がかかります。
高速インターネット接続には月額料金が発生し、学習用デバイスの購入には初期投資が必要です。
N高入る前にMac bookを買わなくちゃいけなかったけど何故WindowsPCではダメなのかな。息子は前の高校でもMac使っていたので問題無かったけど。Macの方がお高い。#n高 #MacBook
— AO推薦入試ママ【合格のコツ教えます】 (@AOkou3mum) March 9, 2022
ただし、一部の通信制高校では学習デバイスの無償貸し出しや、デジタル機器の操作サポートデスクなどを導入しています。
資料請求時には、オンライン学習に必要な環境とサポート内容を確認しましょう。
2. 通学が必要な科目もある
オンライン学習で多くの科目を受講できる通信制高校も少なくありません。しかし、完全にスクーリングをなくすことはできません。
文部科学省の規定では、メディアを利用した学習でのスクーリング代替は最大60%。残りの時間は実際に通学して授業を受ける必要があります。
実技を伴う体育や家庭科の調理実習や理科の実験、美術や音楽などの実技科目は、オンラインだけでは十分な学習効果が得られません。
日本初メタバースを活用して通える通信高校。通信制高校は年に決められた時間数対面でスクーリングを行う必要がある。(最短だと年に一回2泊3日のスクーリングで卒業可能NHK学園など)これもメタバースで賄えればすごい改革だと思うけどスクーリングは必要な様子。一点だけ注意が必要だと感じるのは…
— こうめい|親育て先生 (@yumenochikara39) January 15, 2024
最短でも年間5〜7日程度のスクーリングを設定している学校が多く、この期間に実技科目や特別活動をまとめて実施するなど、効率的なカリキュラムを組んでいます。
通学の必要性を理解した上で計画的にスクーリングに参加することが求められます。
3. 自己管理が必要
オンライン学習がメインの通信制高校では、自由度の高さがある反面、高い自己管理能力が求められます。
教室とは異なり、自宅では気が散ることが多いため、つい休憩時間が長くなったり、授業中に居眠りしてしまったりするケースも少なくありません。
通信制では、各科目で定められた数のレポートを期限内に提出することが単位修得の条件です。
自己管理がうまくいかないと、締切直前に焦ってしまうケースもあります。計画性がないまま学習を進めてしまい、単位を修得できず卒業が難しくなる可能性もあります。
>RT
— えこ (@bambi_eco) November 2, 2022
うちの息子も公立の通信制高校だったので学費が安くて助かりました。教科書代を除けば、年で1万かかってないかも。ただ、自己管理ができないと単位落としまくるだろうなって感じではありました。
学校側も学習管理システムによる進捗確認や、定期的なオンライン面談などの学習サポート体制を用意しています。
しかし、基本的には自分で計画を立て、それを実行する意志力が必要です。
必要に応じて週1〜2回は通学するハイブリッド型の学習スタイルを検討することもできるでしょう。
4. コミュニケーション不足
オンライン学習メインの通信制高校では、先生やクラスメイトとコミュニケーションを取る機会が不足しがちです。
日常的に先生と話せる環境にないことで、レポート提出前に分からない点を質問したり、生活面での相談をしたりしづらい可能性があります。
また、生徒同士の交流も少なくなり、友達を作りづらい可能性も。
グループワークやディスカッションの機会も少ないため、協調性やコミュニケーション能力を育むのが難しい場合もあります。
私は通信制高校卒ですが、高校3年間で友達は一人もできなかった。
— ミコト (@makoto_mikoto) November 18, 2023
それが寂しいとか何とかもない。
中学までの不登校で人間不信がピークに達してたので、人とどう接すればいいのかわからなくなっていた。
友達関係が何かのモチベーションになるような感覚もわからないし。
淡々と課題をこなしただけ。
バーチャル文化祭やオンライン部活動など、新しい形での交流機会を設けている通信制高校も多いです。
様々な地域に住む生徒同士がつながったり、全国から共通の趣味を持つ仲間を見つけたりできるのは通信制ならではの特色。
とはいえ、オンライン上だけではコミュニケーション能力の向上には限界があります。
年に数回のスクーリングやイベントに参加した際には、積極的に交流することが大切です。
【通信制高校に入学・転入したい方へ】
オンライン学習でスクーリングを減らせる通信制高校を探そう
通信制高校でのオンライン学習は、スクーリングの負担を大幅に減らせる魅力的な選択肢です。
年間の通学日数を5〜7日程度まで削減できる学校も増えています。
自分の生活スタイルや学習ニーズに合ったスクーリングを実施する通信制高校を選ぶことで、効果的な学習環境を整えることができます。
サイル学院高等部のスクーリングは年1回のみ。普段の授業はオンライン個別指導で、全国47都道府県から入学・転校できます。
通信制高校を探すなら【サイル学院の資料請求】がおすすめです。
サイル学院は、学校のふつうをなくした『ちょうどいい』学校。完全1対1の個別サポートで高校卒業とその先の進路まで伴走します。全国から毎月いつでも転校生を受け入れています。
▼生徒への質問
▼毎週実施する1on1【切り抜き】
資料請求いただいた方には、サイル学院の学校案内資料に加えて、通信制高校や進路の選び方がわかる資料もプレゼント中です。
「通信制高校のルールがわからない…」
「種類が多すぎてどれを選べばいいか迷う…」
「サイル学院と他校との違いを知りたい」
などの疑問や不安は、サイル学院の資料請求で解決できます。
資料は未成年の方・生徒ご本人も請求いただけます。お気軽に請求ください。
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
.png)
コスパ・タイパよりも、寄り道をしていこう【幸福学の第一人者・前野 隆司教授✕学習塾モチベーションアカデミア代表・佐々木 快さん】
次の記事
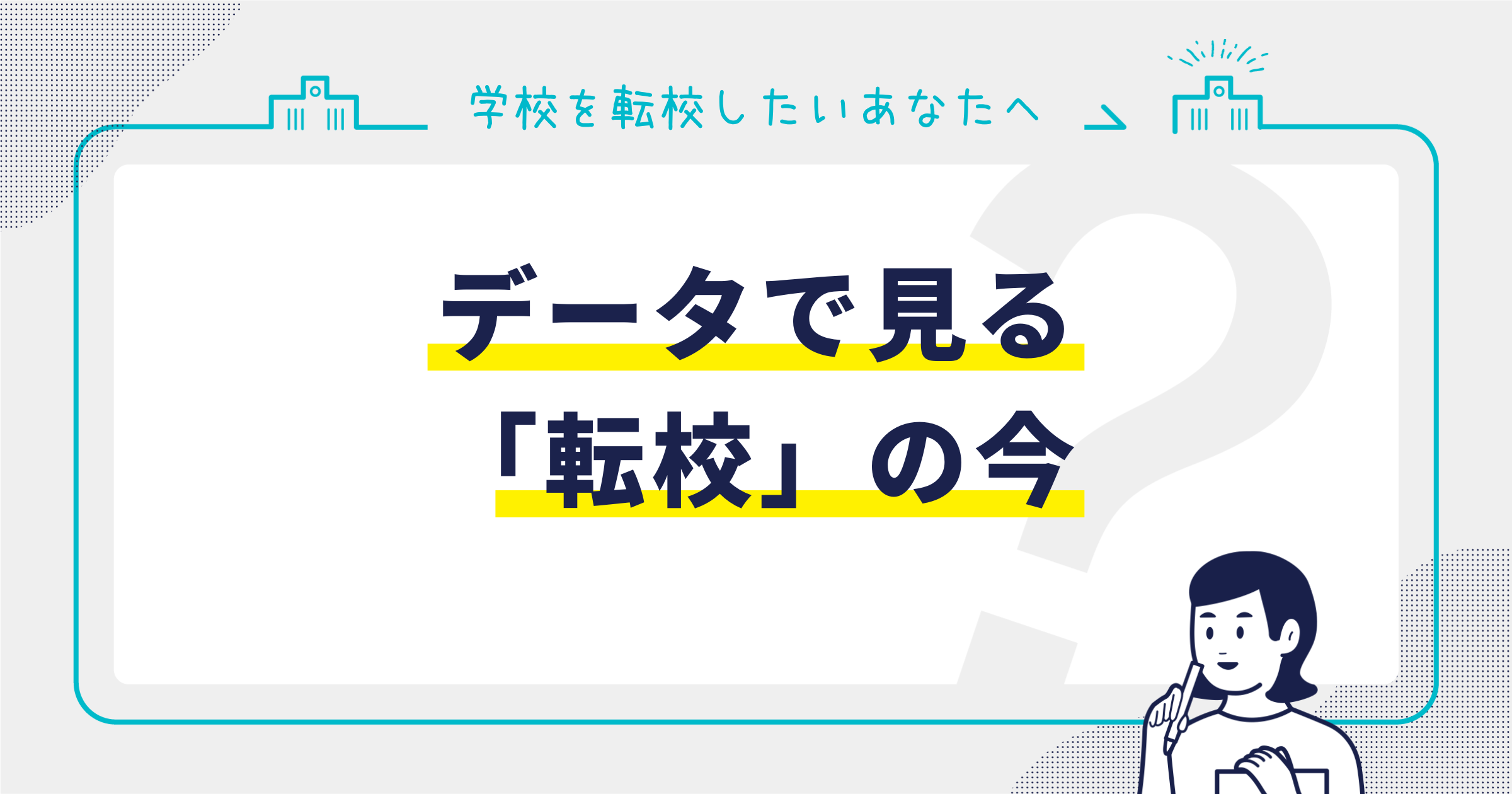
データで見る「転校」の今