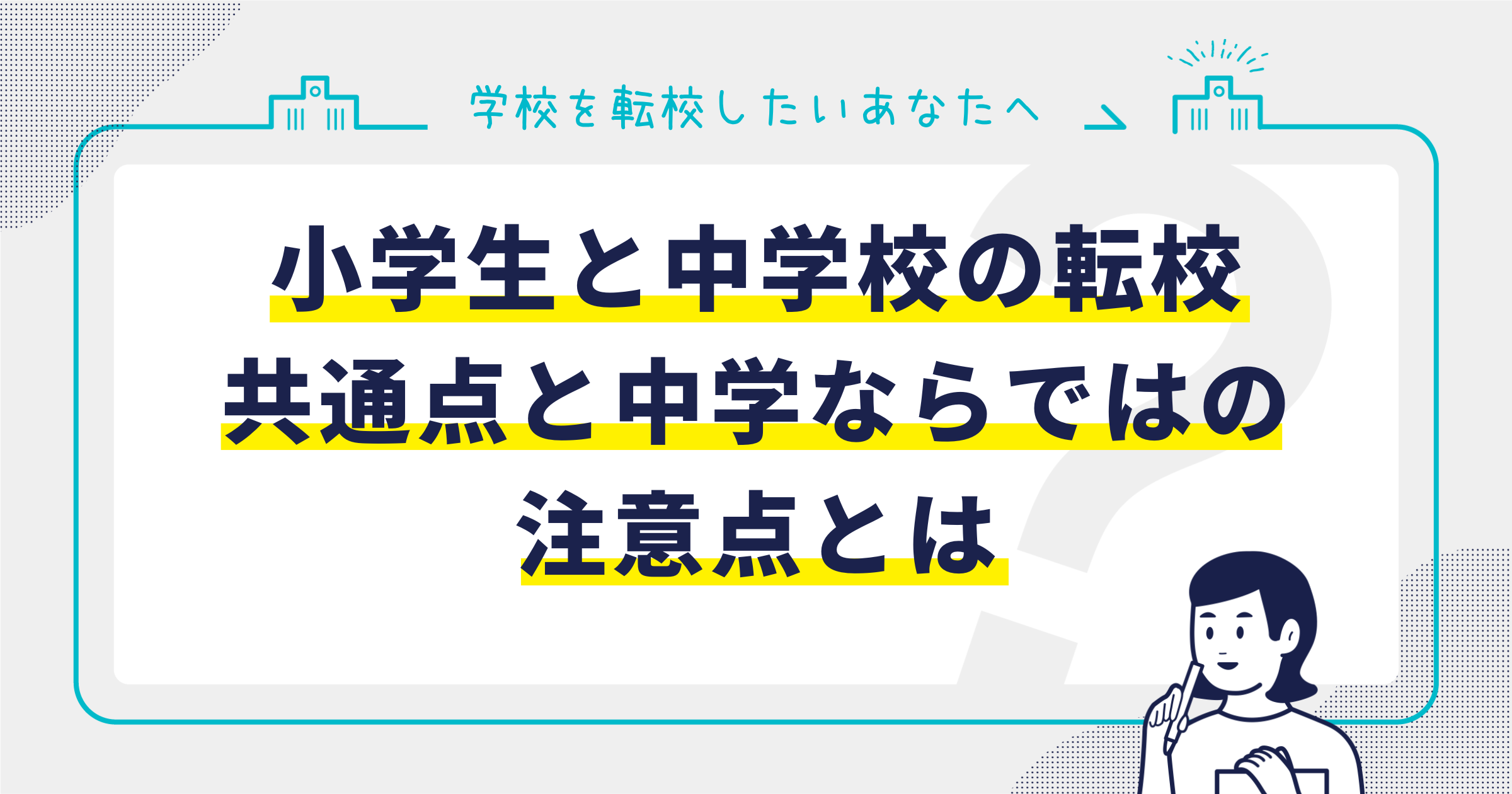公立の仕組みは小学校・中学校で大きくは変わりません。
学区に基づく指定校、「旧校→役所→新校」という基本動線、そして住所を動かさずに通学先だけ変える手続が承認制であること、これらは共通です。
ただ、中学校では「評定(いわゆる内申)」「定期テスト」「教科担任制」「部活動」「進路指導」といった要素が絡み、同じ“転校”でも設計の仕方が違ってきます。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、小学校と中学校の転校の共通点や、中学校の転校ならではの注意点について、進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が解説します。 |
小学校・中学校における転校の共通点
最初に確認したいのは、就学先の決まり方と手続きの流れです。
小学校・中学校ともに、居住地の学区に基づいて教育委員会が就学先(指定校)を割り当てます。
転校の基本的な流れは全国でほぼ共通で、次の3ステップです。
- 旧校で「在学証明書」「教科書(教科用図書)給与証明書」を受け取る
- 市区町村で住民異動(転入/転居)をして就学先の通知を受ける
- 新しい学校へ書類を提出し、初登校や持ち物・連絡手段・時間割など当面の段取りを整える
住所を動かさずに通学先のみを変えたい場合は、小学校・中学校ともに「指定校変更」(同一自治体内)や「区域外就学」(自治体をまたぐ)の枠組みがあります。これは申請すれば必ず通る制度ではなく、基準該当と受け入れ余力を前提とする承認制です。
※詳しくは「中学校における「指定校変更/区域外就学」について」もご覧ください。
また、同一市内の転居時に学年末や卒業まで元の学校に在籍を継続できる運用、入居前から新住所側に通える「先行通学」など、自治体によって独自に提供される制度を利用できることもあります(いずれも利用可否や条件は地域差が大きい)。
さらに、在籍校を変えなくても環境は調整できます。
通級による指導、特別支援学級、校内教育支援センター(別室登校)、教育支援センター(適応指導教室)、フリースクールとの併用、ICTを活用した在宅学習など、子どもに合わせて“場・時間・関わる人”を組み替える手段は小学校・中学校ともに拡大しています。
つまり、「転校」か「転校しないか」だけでなく、“どの段階で・何を組み合わせるか”を設計する視点が共通して重要です。
中学校の転校における6つの注意点
次に中学校の転校だからこそ気をつけるべき注意点を6つ紹介します。
注意点1. 評定(いわゆる内申)の扱い
小学校にも成績の評価はありますが、「内申点」に相当する高校入試用の5段階評定はありません。(*1)
最終的な評定は、転入先の学校が自校の基準で、在籍期間内の学習・提出・出欠などの記録を総合して決めます。
通知表の写し、主要教科のノートや提出物、小テストの結果など、評価の根拠を可視化できる材料をそろえて渡すほど、転入先の判断が安定するでしょう。
注意点2. 定期テストと提出物の“切れ目”対策
テスト範囲や提出締切は学校によって異なります。(*2)
旧校で直近4〜6週間の範囲表と提出一覧をまとめておき、新校では追試・補点の可否、提出の扱い、評価配点の考え方を早期に確認しましょう。
新校の授業が「どこまで終えているか」を見える化できれば、予習計画が立てられます。
注意点3. 教科担任制ゆえの進度差
中学校は教科担任制のため、同じ学年でも単元の並びや教材版、評価観点に差が出ます。
各教科の進度について、新校側に転校時期までの進捗予定を確認しましょう。在籍校との進度の差が分かれば、各教科で予習が必要かどうかわかります。
注意点4. 部活動:登録・安全・合流の段取り
部活動への途中合流自体は一般的ですが、段階的な合流(練習見学→部分参加→全面参加)を前提に体力と生活リズムを整えましょう。
用具・保険・遠征費などのローカルルールも最初に確認しておくと安心です。
注意点5. 進路指導と情報共有
転入面談の段階で、模試の成績推移、学習時間の実態、志望校などを共有しておくと、学校側が課題設定や評価の入口を用意しやすくなります。
中学3年生の転校では、学校ごとの資料参照時期(評定の締め日や提出物の回収タイミング)も早めに確認しましょう。
注意点6. 特別活動・生活記録の扱い
委員会、係、行事参加、ボランティアなどの活動歴は、観点別評価や総合所見に反映される場合があります。
これまでの関わりのメモ(期間・役割・頻度)を簡潔に用意しておくと、転入後の把握と評価がスムーズです。
生活面の配慮(健康・学習・行動)については、要点をまとめて渡すと学校側への意思疎通が速くなります。
*1 「学習評価に関する資料」平成30年12月3日 教育課程部会・児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ合同会議
*2 各学校ごとに範囲表を掲載しており学校ごとにテスト範囲や提出締切が異なる事が分かる例1 岩国市立岩国中学校 / 例2 松江市立鹿島中学校
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事

公立中学校間の転校