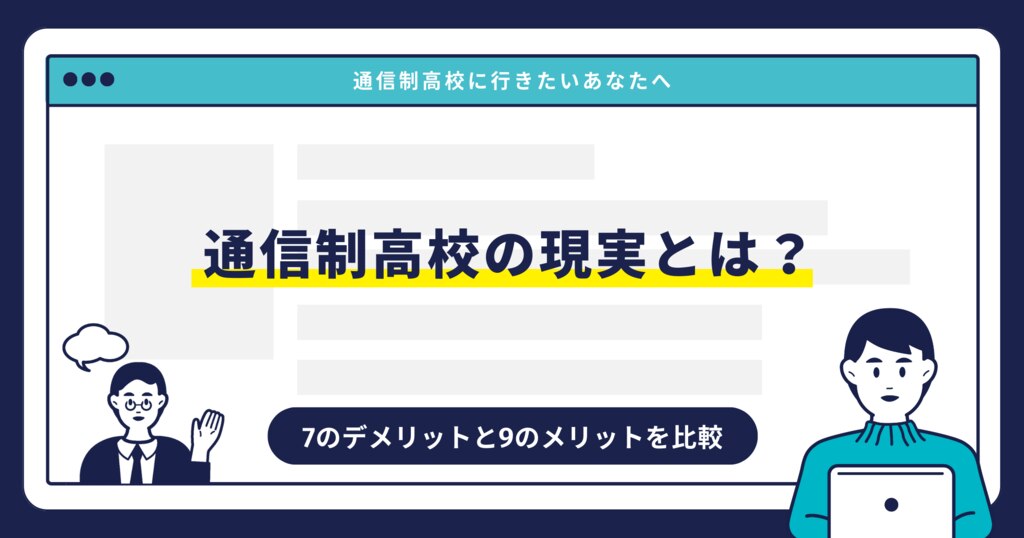記事を読むのにかかる時間 3分
「通信制高校が気になっているけれど、現実はどうなのだろう」と考えていませんか。
通信制高校の実態を知らないと、入学しても良いのかどうかわからないでしょう。
大切なのは、通信制高校の現実を知り、メリットとデメリットを比較すること。
そうすれば、入学するかどうか判断するための十分な情報が得られます。
 通信制のサイル学院長
通信制のサイル学院長
|
本記事では、通信制高校の現実を解説するために進路相談のプロ(書籍「13歳からの進路相談」著者)であり、通信制のサイル学院高等部 学院長の松下が7つのデメリットと9つのメリットを詳しく比較します。 また、通信制高校特有のデメリットを解決する方法や、おすすめの学校も紹介しています。ぜひ、参考にしてください。 |
【通信制高校が気になる方へ】
目次[非表示]
通信制高校の現実|7のデメリット
ここでは、通信制高校の7つの現実的なデメリットを紹介します。
- 自分で学習管理が必要
- レポートが大変
- 分からないことを聞きづらい
- 部活動や課外活動が少ない
- 友達を作りにくい
- 単位を引き継げないことがある
- 大学進学が難しい
通信制高校の現実を知った上で、入学するかどうかを決めましょう。
デメリット1. 自分で学習管理が必要
通信制高校では、全日制高校と比べて中途退学する人の割合が多いです。
|
|
|
中途退学者数(割合)
|
|---|---|---|
|
全日制
|
公立
|
7,867人(0.6%)
|
|
私立
|
12,102人(1.3%)
|
|
|
通信制
|
公立
|
2,696人(5.0%)
|
|
私立
|
6,288人(3.5%)
|
出典:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 P118」
通信制高校では、学習計画や科目選択、時間割を自分で決定します。毎日登校しないため、自主的に学習を進め、レポートを作成する必要があります。
デメリット2. レポートが大変
通信制高校は、自宅でのレポート学習が中心です。
勉強の習慣が定着していない場合、レポート作成を苦痛に感じる生徒もいるでしょう。
@d2_yt うん・・・つらいよ(泣)40枚くらいあるやつを終わらせないといけないし、それと別にラジオを視聴してレポート書くやつが30枚くらいあって・・・バイトしてレポートして学校行ってってマジキツい・・・
— ピエトロ (@Lovemmy0211) February 2, 2015
通信制の高校ってこんなキツいん????
通信制高校では、1単位あたり3~5枚、年間100枚程度のレポート提出が一般的なようです。
レポート提出の方法は学校によって異なりますが、多くの学校は紙での提出が一般的です。
ただし、一部の学校ではオンライン提出も可能。隙間時間を利用して学習を進めれば負担は軽減されるので、各校のレポート提出方法を確認しましょう。
デメリット3. 分からないことを聞きづらい
通信制高校は登校日が少ないため、勉強の不明点を聞きづらいです。
息子①の通信制のレポート提出、順調に進んでいるかと思いきや、めちゃくちゃ溜め込んでた(-""-;)
— たまこ②(旧名えりしや) (@erisia0117) January 4, 2023
全くやってないわけでなく、分からないところなど飛ばしてる感じ…
自分自身で調べて学習を進めたり、積極的にスクーリングの機会を活用したりしなければ、勉強の遅れが生じる可能性があるでしょう。
デメリット4. 部活動や課外活動が少ない
通信制高校は、部活動や課外活動が少ない事が多いです。また、全日制高校に比べると、修学旅行や学校祭など行事も少ない傾向があります。
このため、学校生活を充実させたい方には物足りない可能性があります。
デメリット5. 友達を作りにくい
通信制高校では、友達を作りにくいと感じる人もいます。
友達できない、って嘆くツイートを見た。
— 🐰ウサコ🐰 (@takana66692994) April 8, 2023
長男が通信制高校入学して直後に先生に言われたのは
『友達はなかなかできないと思いますよー(他の子も同様)😅』
でした。
『まずは学校に慣れていきましょー😊』と。
マジそれな、です。
特にスクーリングが少ない学校に通っている場合、同級生との交流の機会が少ないです。
積極的に課外活動に参加したり、イベントに参加したりしなければ、人との接点が少ないまま学校生活を送ることになるかもしれません。
デメリット6. 単位が引き継げないことがある
全日制高校から通信制高校へ転校を考えている場合、引き継げる単位数を確認しましょう。
全日制高校は学年末に単位を修得する仕組み。
年次の途中で通信制高校に転入する場合、その学年の単位は引き継ぐことができません。
また、工業科・商業科から普通科への転校の場合、一部の単位が引き継げないこともあります。
転入前に、志望する通信制高校に相談しておくと良いでしょう。
デメリット7. 大学進学が難しい
もともと通信制高校は、勤労青年に高等学校教育の機会を提供するものとして設立されたため、大学進学を前提としたカリキュラムになっていない学校もあります。
季節ごとの講習や模擬試験、補習などの機会が少ないため、受験対策が十分に行えないこともあるでしょう。
進路情報の収集や志望校の受験対策を自分で行わなければならないため、全日制高校と比べて大学進学のハードルが高い場合があります。
【通信制高校が気になる方へ】
通信制高校の現実|9のメリット
ここでは、通信制高校の現実的なメリットを9つ紹介します。
- 自分のペースで学習できる
- 通学頻度を自分で選べる
- 専門的なカリキュラムがある
- 自分のやりたいことと両立できる
- 入学しやすい
- 留年がない単位制が多い
- 様々な事情を持つ生徒に対応してくれる
- 先生からサポートを受けやすい
- 人間関係のストレスを抱えづらい
メリットとデメリットを十分に比較検討してみましょう。
メリット1. 自分のペースで勉強できる
通信制高校の学習形式は、レポートと呼ばれる問題集が中心です。レポート学習のメリットは、自分のペースで勉強できること。
通学は月数回~年数回程度。スクーリング日以外は自分のペースでレポート学習を進めることができます。
自宅や移動時間などの空き時間を活用して学習することも可能です。
また、単位を着実に修得するため中学教科の学び直しや習熟度別授業を設けている学校もあります。
メリット2. 通学頻度を自分で選べる
通学頻度を選べるのも通信制高校の魅力のひとつ。
登校頻度や時間を調整できるため、不登校や体調に不安のある方でも安心して通えます。
途中で通学頻度などを変更できる学校もあります。
最初は在宅コースや週1~2日のコース、慣れてきたら毎日通学コースに切り替えるのも現実的です。個人の希望に合わせて柔軟に対応してくれる学校も多いです。
メリット3. 専門的なカリキュラムがある
専門科目を学べる通信制高校なら、高校在学中に資格や専門知識を身につけられます。
私立の通信制高校は多様な専門分野を提供している学校も多いです。
個々の興味や進路に合わせて現実的な専門科目を選ぶことができます。
【通信制高校が気になる方へ】
メリット4. 自分のやりたいことと両立できる
通信制高校では、スクーリングの日以外は時間を自由に使えます。
そのため、自分のやりたいことと勉強を両立できるのがメリット。
例えば、アルバイトやパート、正社員として働きながら高卒資格を取得することも可能です。
また、芸能活動やプロスポーツ選手としての活動、海外留学や国家資格の勉強など、卒業後の目標や夢を実現するための準備を高校在学中に並行して進められます。
【くわしく読む】「自分の好きな勉強を、好きなだけできるので楽しい」全日制の進学校から通信制に転校した、新潟県在住の生徒
メリット5. 入学しやすい
通信制高校は、基礎学力を判断する学科試験(国語・数学・英語)や、作文・面接を実施する学校があります。
書類審査のみで入学できる学校もあるため、各校の募集要項をよく確認しましょう。
![]() 入学までの流れ(サイル学院高等部の例)
入学までの流れ(サイル学院高等部の例)
- WEB出願(オンライン)
- 入学面談(オンライン)
- 出願から合否連絡までは約1週間
転校(転入・編入)しやすいのも通信制の特徴。転校できる時期を選べる学校が多いです。
メリット6. 留年がない単位制が多い
通信制高校の多くは「単位制」であり、留年の心配がありません。必要な単位数(74単位)を修得できれば卒業することが可能です。
もし単位を落としても、翌年に再挑戦して単位を修得し直すことができます。
また、全日制高校から通信制高校への転入の際には、以前の学校で修得した単位を引き継げる可能性があります。
転校後の頑張り次第では、同級生と一緒に卒業できるかもしれません。通信制高校を選ぶなら、単位を修得しやすい学校を候補にしましょう。
メリット7. 様々な事情を持つ生徒に対応してくれる
通信制高校には不登校経験のある人や、様々な事情により中途退学した経験のある人が多く在籍しています。
学習障害や持病を抱えたりしている生徒も在籍しています。そのため、特定の支援が必要な生徒に対して、個別のサポートや相談窓口が用意されている学校もあります。
メリット8. 先生からサポートを受けやすい
通信制高校では、登校日が少ないので先生から直接指導を受ける機会が限られています。
そのデメリットを補うため、個別に先生からサポートを受けやすい環境が整っている学校が多いです。
私立の通信制高校では、学習・メンタル・進路指導などの支援が提供されています。
例えば、提出期限が近づいたレポートを知らせてくれる学校や、チャットやメールで質問できる学校もあります。
メリット9. 人間関係のストレスを抱えづらい
通信制高校の多くは、人間関係のストレスを抱えづらい環境を整えています。
通学頻度が低く、クラスメイトや担任の先生との相性によるストレスを軽減しやすいです。
クラス規模も少人数の学校が多く、人間関係に不安を抱える生徒も安心して学校生活を送れるでしょう。
また、専門科目を学ぶ学校では、同じ関心や興味を持つ仲間と出会いやすく、友だちができやすいのも特徴です。
まとめ
通信制高校にはデメリットもメリットも存在します。
一方で、何をデメリットやメリットと感じるかは人ぞれぞれです。
他人が決めたデメリットやメリットを鵜呑みにせず、自分で判断しましょう。
通信制高校を探すなら【サイル学院の資料請求】がおすすめです。
サイル学院は、学校のふつうをなくした『ちょうどいい』学校。完全1対1の個別サポートで高校卒業とその先の進路まで伴走します。全国から毎月いつでも転校生を受け入れています。
▼生徒への質問
▼毎週実施する1on1【切り抜き】
資料請求いただいた方には、サイル学院の学校案内資料に加えて、通信制高校や進路の選び方がわかる資料もプレゼント中です。
「通信制高校のルールがわからない…」
「種類が多すぎてどれを選べばいいか迷う…」
「サイル学院と他校との違いを知りたい」
などの疑問や不安は、サイル学院の資料請求で解決できます。
資料は未成年の方・生徒ご本人も請求いただけます。お気軽に請求ください。
【通信制高校が気になる方へ】
この記事を書いた人

13歳からの進路相談 著者/サイル学院高等部 学院長
1993年生まれ。福岡県福岡市在住。一児の父。株式会社13歳からの進路相談 代表取締役社長。著書『13歳からの進路相談』シリーズは累計 16,000部突破。続々と重版されてロングセラーとなり、全国の学校や市区町村の図書館で多数採用されている。
学生時代は早稲田実業学校高等部を首席で卒業し、米国へ留学。その後、早稲田大学政治経済学部を卒業。やりたいことではなく偏差値を基準に進路を選び後悔した経験をきっかけに、大学在学中に受験相談サービスを立ち上げる。これまでに寄せられた中高生からの相談は10万件を超える。大学卒業後は教育系上場企業とコンサルティング会社で勤務。
2022年に株式会社13歳からの進路相談を設立し、代表取締役に就任。一人ひとりが自分に合った進路を選べる社会を目指し、「
サイル学院高等部(通信制)」を創立。全国から入学・転校生を受け入れ、高校卒業だけではなく、その先のキャリア支援も行っている。
著書:『
13歳からの進路相談(すばる舎)』、『
13歳からの進路相談 仕事・キャリア攻略編(すばる舎)』(紀伊國屋書店 総合週間ランキング 玉川高島屋店1位、新宿本店2位)
前の記事
.png)
コスパ・タイパよりも、寄り道をしていこう【幸福学の第一人者・前野 隆司教授✕学習塾モチベーションアカデミア代表・佐々木 快さん】
次の記事
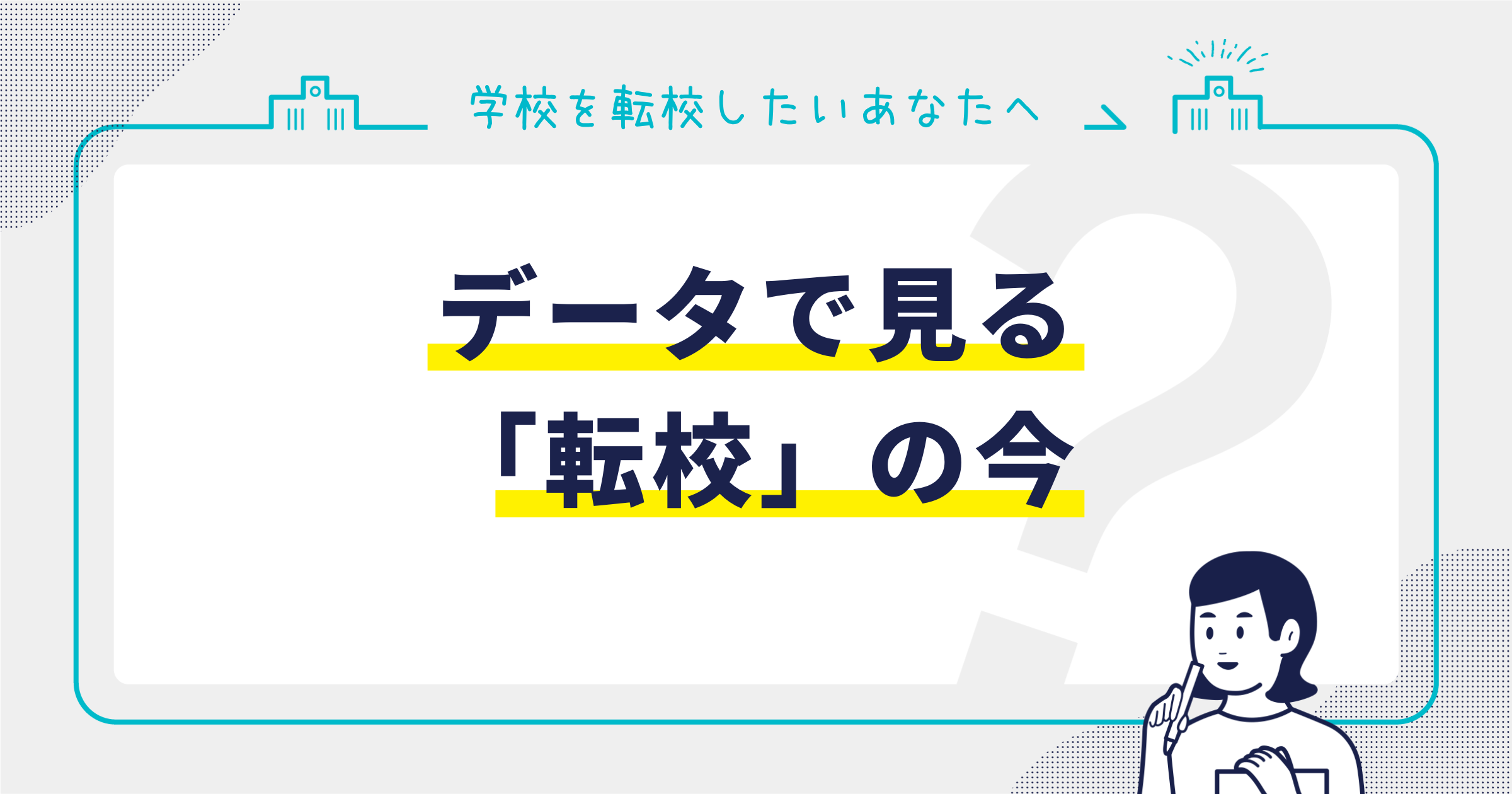
データで見る「転校」の今